人は、何か「大きなもの」に没入したいという傾向を持っている。世界観や価値観も統合した世界理解の大きな枠組みのことである。それによって自己の居場所を世界の中にあたりまえのものとして感じられるし、また、その「大きなもの」は、価値や行動の規範を与えてくれる。さらに、その「大きなもの」は通常まわりの人たちと共有されるので、人々と連帯することもできる。深く悩まずに人々とともに安心して暮らせるのだ。
「大きなもの」は、大抵、昔からあらかじめ存在するものとして与えられる。人はその中に生まれ育つ。「大きなもの」は、本来、人が自由に取捨選択できる対象ではない。受け入れられ、信じられなければならないものだ。
「大きなもの」は、歴史的あるいは風土的には一定の必然性を有する。しかし、歴史や文化を超えた普遍性は持たない。別の時代、別の土地に行けば、あざけりの対象にさえなり得る。「大きなもの」は偶然の産物なのだ。それゆえ、正しいかどうか、絶対的であるかどうかといった合理的客観的な検証には耐えられない。疑われれば、たちまち揺らぎはじめ、崩壊してしまう。
だからこそ、もし集団の中にその集団の「大きなもの」を共有しない人がいれば、攻撃される。自分たちの「大きなもの」が絶対的でなく、相対的・恣意的なものであることが暴露されてしまうからだ。
例えば、わたしが「国旗に一礼しない村長」として話題になったとき、たくさんのハガキやメールが送られてきた。賛同と非難の両方があり、賛同は長い文面が多かったが、非難については、「日本人なら例をするのは当然」「国旗への礼は世界の常識」「バカ村長」というような断片的、断定的なものばかりだった。
そういう非難に対してこんな質問を返した。
「国境線はしばしば動く。昨日までA国だった地域が、今日からはB国ということもある。複数の国がひとつになったり、逆に一つの国がいくつかに分裂することもある。そのたびにそれに対応して新たな国旗に礼をするのか?」
非難には中国嫌いの右寄りのトーンを感じたので、「日本が中国領になったら、あなたは五星紅旗に礼をするのか?」「チベットやウイグルの人はみんな五星紅旗に礼をすべきと言うのか?」と問うた。回答はなく、やがて非難の声は届かなくなった。
国旗への礼の強要には、万人を納得させるだけの合理的説得力はないのである。
「大きなもの」としてなにを仰ぎ奉るかは、その人のアイデンティティの問題だ。他人が人に指図することではない。にもかかわらず、一部の人たちは、ともかく圧力をかけて礼をさせ、自分たちの「和」を乱させないようにしたいのであろう。それを端的に示したのは、「心の中で舌を出していてもいいから、ともかく礼をしろ」という露骨な要求だ。
わたしは、礼をするのなら納得して心から礼をしたい。心の中で舌を出しながらの礼など、逆に侮辱ではないかと思う。
国旗への礼を強要する人たちは、国旗が大事なのではなく、「大きなもの」にみんなで一体化して得られる自分たちの安寧を守りたいのだ。
ところで、なぜわたしは「大きなもの」への没入圧力をかくも嫌うのか。
私の考えの根本は、釈尊の教えだ。釈尊の教えは、「大きなもの」にみんなで没入せよという同調圧力を拒絶する。
今これを読んで、逆ではないかと思った読者もいるだろう。確かに歴史を振り返れば、仏教も含めて宗教全般は、どちらかといえば集団への帰属を後押しすることの方が多かった。極端な例を挙げれば、戦場で突撃して銃弾に撃たれ「天皇陛下万歳」と叫んで倒れる瞬間こそ、阿弥陀如来の本願が発露する極致だと主張し、天皇のために戦争で死ぬことを奨励した例もある(『親鸞と日本主義』中島岳志、新潮選書)。
逆に、宗教が国家などの大きな集団に立ち向かった場合もあるが、それはその教団が取りまとめる集団が結束して闘ったのである。宗教そのものが、一種の「大きなもの」となり人々を集団化させてきた。人々に基盤と価値と規範を与え、安心させてきたのである。
しかし、釈尊本来の無我の教えは、「大きなもの」への帰属とは相容れない。そもそも、帰属すべき「我」がないのである。その点でも、釈尊の教えは極めてユニークだ。
そんなことを考えていて、一本の数直線上に「大きなもの」のバリエーションを並べてみることを思いついた。
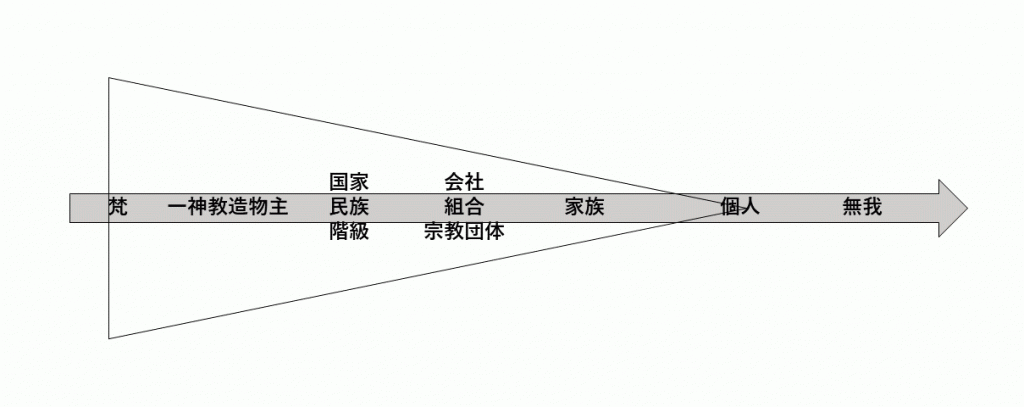
数直線の左ほど「大きなもの」は大きく、右に行くにしたがって小さくなり、「理想的(目指すべき、という意味ではなく、理論上の純化した、という意味)」な完全な個人に至って「大きなもの」は消失する。いろいろな「大きなもの」を並べることができるだろうが、わたしなりにモデルとして例示してみた。
(考え方を示すためにいくつかサンプル的に並べているだけなので、個々の「大きなもの」についての詳細な議論はご勘弁を。)
一番左には「梵」を置いた。梵は、バラモン教ウパニシャッドの考えで、世界・宇宙の全体であり、すべてを生み出す本源であり、またすべてを包摂する。すべてであるから、善も悪も美も醜も清も濁も内包する。対立概念をもたない。個物に対する全体ということもできない。ともあれ、すべてを超越しつつ、同時にすべてでもあり、絶対的に肯定すべきなにかである。本来言語化できない。否定を重ねることによって、ようやく間接的に言及することができる。徹底的に対立するものを廃した全体であるので、左端に置いた。
その次には、唯一神の造物主・創造神を考えることができる。世界の全体を創造したとされるが、おそらく神自身は、創造主として創造した世界の外に超越しているのだろう。また、現実世界にあるさまざまな悪については、悪魔によるとしており、善なる神は、悪や悪魔とは対立している。世界の中の悪は神の側にないのであるから、梵よりは領域が狭いと言える。もっとも、悪魔そのものも、元は神の創造物であり、神を裏切った天使とされるが、ともあれ、世界の中に対立するものが存在する分だけ、数直線上では少し右に位置する。
その右には、国家や民族を置くことができる。国家を統治する者たちは、自分たちの都合で国民にしばしば強烈な同調圧力をかける。同じ理由で、民族を団結のために利用することもある。また、団結を強固にするため、時として他国、多民族への憎しみを煽る。国家の統治に対抗するため、民衆の側が民族の結束を呼び掛ける場合もある。階級の団結が訴えられることもある。これらは、内側への同調圧力は強くても、外側に他国や他民族、他階級の存在を自明としているから、「大きなもの」としては、それだけカバーする範囲が狭い。
その右には、企業や組合、宗教などの団体・組織がくる。それぞれがなんらかの価値や目的の共有をメンバーに要求、ないしは期待している。朝礼をして、組織の精神を短くまとめた言葉を唱和し組織の歌をみなで唄う。
さらに小さくなると家族がある。家族への帰属は、普段はさほど意識されないが、いざというときには強く発揮される。
国家への没入を要求する人たちは、しばしば家族を尊重すべき価値として強調する。家族は自然な集合体であり、国家を疑似家族として印象づけることによって、それへの帰属も「自然なもの」だと印象付け、疑念を抱かせずに取り込もうとする。
ところが、家族は、時としてそのメンバーへの圧力として作用し、意に沿わないふるまいを強制する封建的性格を有することも珍しくない。家族に例えて国家が国民の前に掲げられる時、ほぼ例外なく、その国家は国民に勝手な行動を許さない抑圧的「家族国家」である。
家族より右には、個人がある。勿論、個人でも現実には左に並ぶいずれかの「大きなもの」に帰属する場合がほとんどだ。ここでいう個人とは、どれかの「大きなもの」に形式上は帰属していたとしても、その世界観や価値観、規範などを共有せず、共感していない人のことである。玉ねぎの皮を一枚一枚剥いでいって、最後に残った小さな一かけらのような、「大きなもの」に包まれないむき出しの個人だ。さまざまな「大きなもの」が、恣意的であり絶対ではなく、歴史の中の偶然の産物、思い込みにすぎないと理解し、「大きなもの」をしがらみだと感じている。この人にとって、同調圧力は煩わしい。面従腹背して「心の中で舌を出して」同調しているふりをしながら、めんどくさい、ばかばかしいと感じている。面従腹背さえしない、正直で腹の座った人もいる。
ではしかし、さまざまな「大きなもの」が要求してくる世界観や価値観、規範を、すべて軽蔑し共有しない個人は、好き勝手に自由気ままにふるまえるのだろうか。
残念ながら、そうはならない。あらゆる「大きなもの」を脱ぎ捨てれば、自分の寄って立つ基盤も、行動規範も失う。なんでもできるはずなのに、なすべき価値も目的も持てない。『ツァラトゥストラ』の「三段階の変身」の幼な子のように価値を問うことなく無邪気に遊んでいることは、たやすくはない。
若いころ、自分を動物園の熊のように感じていた。檻の中をただぐるぐると行ったり来たりしつづけている。しかし、檻などないのである。檻どころかなにもない。星のかけらも見えない暗黒の広漠たる宇宙にひとり浮かんでいる熊のように感じていた。上下左右前後、すべて漆黒の空間がひろがるだけで区別がない。そんな空間で移動したとしても、移動に意味があるだろうか。
すべての「大きなもの」から離脱し、すべての価値が価値を失えば、行動も意味を失い、目的をもって何かに取り組むこともできなくなる。
家を捨てる前の釈尊も、実はこのようではなかったか。社会状況が大きく変わる時代であり、バラモン教という「大きなもの」も統率力が低下していた。そんな中で釈迦族の将来と妻子とを背負う役割を期待されていたのだが、それが生涯を捧げるに値するか、釈尊は疑問を持った。真になすべきはなにか、自分はどう生きるべきか、自分とは何か、煩悶していたと想像する。
歴史の流れは、数直線上を左から右に進んでいく。かつては社会と社会の間の交流は乏しく、人は生まれ育った社会の中で、その社会の「大きなもの」だけに育まれて成長した。ところが、時代とともに、移動やコミュニケーションの手段が発達し、違う社会の別の「大きなもの」の存在も人々は知るようになった。個人の前にいくつもの「大きなもの」が並立するようになったのである。しかし、多くの場合、「大きなもの」は互いに矛盾し両立し得ない。排他的である。個人は、どれかを選択せねばならなくなる。「大きなもの」は、タブーであった比較検証をされることになる。
また、自然科学の知見との矛盾という脅威にも「大きなもの」は晒される。
こうして「大きなもの」は合理的審判の前に引き出され、絶対的権威を失っていく。
「大きなもの」が崩壊していくことは、その中に生きる個人には不安となる。望まないにもかかわらず、心構えもできていないのに、寄って立つ基盤も規範も失い、むき出しの個人として一人生きていかねばならない。その恐怖から、その変化を見て見ぬふりをする人は多い。疑念を隠し、あたかもなにも変わらず「大きなもの」は安泰であるかのように振る舞う人もいる。
あるいは、もはや絶対性を失った「大きなもの」に無理やりしがみつき、ことさらにその価値を叫ぶ人も出てくる。しがみつく本人が、「大きなもの」のほころびを感じ、自分の寄って立つ基盤の揺るぎを恐れるが故のしがみつきであるから、そのしがみつきは、理性を欠いた狂信にならざるを得ない。古い価値に根差したかつての安定を維持しようと懸命になり、そのためには目障りな異分子は排斥しようとする。排外主義であり「在日」認定である。(わたしも一度「在日」認定をされたことがある。「在日」とは、自分たちと同じ「大きなもの」に平伏せねばならないのにそれをしないけしからぬ輩、という意味だと分かった。かつての「非国民」と同じである。)
これまでどおりの自分を装うことも、しがみつきも、無理やりの不自然な努力である。それゆえ、「大きなもの」を共有しない人への攻撃など、たくさんの苦を生む。しかしそれでも、それほど長くは持続できない。所詮は、自分を欺く努力だからである。
世の中は時代とともに長期的には数直線の右に移行していく。無理やりのしがみつきなどといった一時的な揺れ戻しを繰り返しながらも、むき出しの個人が次第に右端に溢れてくる。彼らは、先に書いたとおり、目指すべき目的も価値も失って、ひとつところで悶々としつつ右往左往するしかない。
そのような右端に溜まって行き詰まる人たちは、どう生きればいいのか。玉ねぎの芯の最後の一かけらには、どのような活路が可能なのか。
それを2500年前にやってのけたのが、釈尊だ。釈尊は、「大きなもの」ばかりか、「我」という最後の一かけらさえもが思い込みであったと認識し、幻影を握りしめる拳の力を解いた(無我)。目的や価値や意味を乞い求めることなく、目的も価値も意味もない生を生きる安らぎを見出した。苦をつくることのない平安を発見したのである。
以前、「人生に意味も価値も目的もないのなら、わたしに死ねということか」という怒りのメッセージを貰ったことがある。意味がないものは存在してはならない、という考えが、そもそも思い込みだ。
最近では、「生産性」で人を評価して非難を浴びた政治家もいた。おそらく生産性と価値とを同一視しているのだろう。なにをどれだけ生産すれば、どんな価値が生まれるというのか。目先の経済しか考えていない。
生産能力の目いっぱいの生産をして、それを必死で販売し、必死で消費させる。その結果もたらされるのは、資源浪費と環境負荷と人々の疲弊でしかない。それが今の社会の現状だろう。かつてわたしは、「人々は究極の価値がないことを薄々感じながら、それを直視することを恐れ、そこから目をそらすために互いに懸命に追い立てあっている」と考えていたが、あながち的外れではなかったかもしれない。
「大きなもの」がぼやけていき、その支配力が衰えるにつれて、個人は自由になっていく。しかし、同時に、自明と思われていた意味や価値も失われ、個人は、新たな指針を求めて右往左往するしかない。このような「裸の個人」を、釈尊の無我の教えは救ってくれる。意味や価値を求めるのは、結局は自分に意味や価値を与えたいという我執なのだ。釈尊の無我の教えは、意味や価値を与えるべき自分がそもそも存在しないことを教えてくれる。意味や価値の問いから根本的に解放されるのだ。
釈尊の教えは、「大きなもの」の虚妄性をあたりまえのこととして受け入れることを可能にし、意味や価値を求めることも無駄な執着であったと教えてくれる。さらにまた「大きなもの」への向き合い方にも変化をもたらす。特に国家に対して顕著だ。批判的であることを要請するのである。
国家の虚妄性に気が付いても、それは消え去るわけではない。相変わらず存在しつつけ機能し続ける。国家は大きな力を持っており、それによって個人や社会は大きな影響を受ける。
国家は、凡夫の寄り合い所帯であり、政治的指導者もまた凡夫である。凡夫が執着の反応のまま繰り返し間違いをしでかし、苦をつくってしまうように、国家もその巨大な力をしばしば苦をつくる方向に発揮してきた。釈尊が戒の教えで、苦をつくらぬよう自分という反応に気をつけていなさいと諭したように、我々も、国家が今どんな反応をしようとしているのか、いつも気をつけていなければならない。国家の力を、反対に人々の苦を減らす方向に使うのだ。
国家は、しばしば「大きなもの」として、メンバーに一定の価値観や世界観を強要する。その力が強い時は、たいてい大きな苦をつくる方向に動いている。釈尊の教えに則って、苦を減らしたいと考えるなら、国家の動きにいつも気をつけて、国家が苦をつくろうとするときには、人々とは違う声を上げ、国家の力の方向を正していかねばならないのである。世界中の人々から苦を抜こうと努力する国だと思えたら、わたしも誇りに感じることができ、国旗に礼をするかもしれない。
*****
以上がこの小論で書こうと思ったことだ。
ところが、先日、拙著『「苦」をつくらない』にご質問を頂いた。オーストラリア在住のアマノさんという方からだ。
「無常=無我=縁起」は自分も以前から考えていたし、理性的であり納得する。しかし、当地の大学教授やITの権威でも、宗教や死後のことになると、まったく非理性的であることに驚く。特に一神教の三大宗教を信じる人たちに、無常=無我=縁起を理解してもらうにはどうすればいいのか」
「大きなもの」に支えられ、そこに安住している人に無常=無我=縁起を語っても、理解してはくれないだろう。また、「大きなもの」に内心の疑念を抱きながら、気づかないふりを装っている人や、なんとか「大きなもの」を倒れないように支えつつ、しがみついている人もいる。この人たちを論破して説得しようとしても、冷笑され相手にされないか、もしさらに追い詰めれば、怒り出すかもしれない。それは得策ではない。アマノさんが例示した知的エリートたちは、多分内心に疑念を抱きつつ、それをつきつめることを避けているのだろう。
しかし、いずれにせよ、それはごまかしだ。いつまでもごまかしとおせない。また、先に書いたように、地球が「小さくなる」につれて、多くの「大きなもの」が横並びに相対化していく。科学の新たな知見の脅威にも晒される。一部の人が一時的に狂信する揺れ戻しがあっても、「大きなもの」は長い歴史のなかで着実に力を失っていく。
だから、今の時点ですべきことは、特定のターゲットを論破しようとすることではなく、「無常=無我=縁起という捉え方もあり得る」という程度であってもよいので、無常=無我=縁起の種をタンポポの綿毛のように風に任せて飛ばし、それが縁を得て芽を出すことを待てばいいのではないかと思う。
多くはないが、無常=無我=縁起になにか新たな可能性を感じる人は確実にいる。焦ってはかえって変化を妨げる。縁を広げていけば、無常=無我=縁起は遠からず必ず根付くと思う。そうでなければ、人々は行き詰ってしまうのだから。
仏教に改宗させようなどとは考えていない。そんな必要はない。そもそもわたしはいかなる宗教団体にも属していない。ただ単に、無常=無我=縁起という自己理解が広がればいいと思う。アマノさんがいうように、理性的に仕事をする学者やIT研究者でも、宗教や死後観では伝統的な考え方に留まっていられるのなら、自分たちの宗教を引き続き信仰しつつ、無常=無我=縁起の合理的理解を深めてもらうことも可能だろう。それは、世界の全体的な執着のレベルを下げることにつながり、世界の苦がいくらか減ることになると期待する。
2018年11月1日 曽我逸郎


