2004年7月26日
仏教、すなわち無我=縁起、の視点から、クオリアとホムンクルスを考えてみたいと思う。
茂木健一郎『脳内現象』(NHKブックス)を読んで大変刺激を受けたのだが、無我=縁起こそ正しいと思う私の立場からすると、若干気になることもあった。「私がある」という我論的解釈をさせてしまう余地があるのではないか。
例えば、
<メタ認知的ホムンクルスが、脳内を見渡し、「小さな神の視点」を獲得して、意味を見出す。>
というような表現がそうだ。
ただし、茂木さんは、
<神経細胞の活動の間の関係性が、主観性の枠組み(ホムンクルス)をつくる。(P195、一部要約)>
とも言っておられるから、「初めにホムンクルスありき」の考えではないのだろう。しかし、不注意な読者は、我論的印象を受け取りかねない。
茂木さんが仏教徒かどうかは存じ上げないし、仏教徒としてこの本を書かれた訳ではないだろうから、こんな批判はお門違いであろう。そのことは承知してい る。それに我論になんら問題を感じない「仏教」徒も多い。唯識系の方なら、メタ認知的ホムンクルスという考えに共感さえ抱かれるかもしれない。しかし、無 我=縁起こそ仏教だと考える私としては、ホムンクルス常住論が増えては困る。無我=縁起の立場から、縁によって起こされるそのつどの反応として、私という 現象を考えてみたい。
メタ認知について極簡単に紹介しておこう。
<自分がそのような形で世界を認識していること自体を、いわば外側から認識し直す心の動き>(『脳内現象』P68)
<人間は自己の内側にあるものを認知すること(メタ認知)しかできない。私達が普段客体として外に認識しているつもりのものは、内部に立ちあがる仮想的対象を外にあるかのごとく認識しているのである。>(同書P192前後を要約。詳細は、同書参照下さい。)
茂木さんは、成人(成長した大人)を想定して論を立てておられるのだろうと思う。成人には様々な「内部の反応の仕組み」があり、その中にはメタ認知的ホ ムンクルスとして捕らえることのできる仕組みもあろう。しかし、私の能力ではすべての仕組みが備わった成人をいきなり考えると収拾がつかなくなりそうだ。 変わりばえのしないアプローチだが、動物進化の視点から、縁によって「私」という現象が起動してくる道筋を段階を追って考えよう。その過程は、今の我々と いう現象の、現象の仕方にも反映されているに違いない。もしそうなら、陥りがちな「我論」、<まず我があり、我が万事を采配している>という自然な考え を、「そのつどの反応の連鎖」に解体してくれる筈である。
おおまかな考え方を共有していただくために、この図を見て頂きたい。
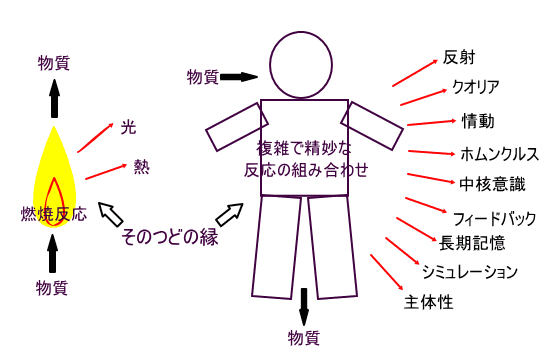
我々は、ロウソクの炎と同様に、物質が通って行く場における反応によって生じる現象である。反応は、そのつどの外部からの縁とその時その 時の内部の状況とに応じて、様々に変化する。そして、その結果生じる我々という現象も、多様に変化する。進化の初期から続く単純な反応である場合もあり、 進化の過程で積み重ねられてきた複雑な反応である場合もある。それら様々な反応を、一旦分解し誕生の順に組み立てなおしてみたいと思う。
① 反射
最初に、生命についての定義めいたものを提示しておきたい。定義といえるようなものではなく、単にひとつの特徴を述べただけかもしれないが、間違ってはいないだろう。
生命とは、反応の組み合わせであり、組み合わせを構成するそれぞれの反応によって、その反応の組み合わせが持続され、拡大されるような反応の組み合わせである。
仏教的に言いかえれば、生命とは反応が反応自身に縁を与える我執の反応である、と言うこともできよう。この、生命の本性たる我執こそ、無明の出所・由来だと考える。したがって、我執・無明を超えようとする仏教は、生命であることを超えようとする挑戦なのだ。(「辞めようとする」ではない。誤解なきように。)
この本性によって、生命は、本来、生命反応の持続・拡大にプラス、マイナスの影響をもたらすこと(利害に関わること)にしか、反応しない。
考えているのは、例えばホメオスタシスである。一例を挙げれば、細胞内のイオンのバランスが偏ってくれば、それに感応するイオンチャンネルが自動的に開き、不足しているイオンを取り込み、多すぎるイオンを汲み出す。その結果、細胞の活動は安定を維持する。
ゾウリムシは、水温が適温を外れると繊毛運動が活発化し、ランダムに動き回る。適温に行きつくと運動は低下するので、結果的に適温域に集まることができる。
また、ヒトデの水槽に餌を入れると、ヒトデはほとんど迷走せずに餌に集まるそうだ。餌から溶け出す科学物質が縁となって、感覚器を刺激し、神経細胞を信号が伝わって、しかるべき移動が起こる。
このような反応は、多くの反応が精妙に組み合さって起こるのだが、言ってみれば機械的である。出会った縁が引き起こす反応は、生得的な身体の仕組みによって決まっており、後天的学習によって反応が異なることはあり得ない。
愛媛大の宮脇恭史先生からお聞きした御意見。「ヒトデは感覚器も中枢神経もそれほど発達しておらず、ヒトデの行動実験や調教実験をやったという話も聞かない。ヒトデに学習能力があるとは考えにくい。後口動物では、ヒトデと魚類の間、ナメクジウオ辺りに学習能力獲得能の境界線があるのではないか。」
勿論、ヒトデの例でいうなら、なにかをたくさん食べた後であったりとか、水温が普通でないとか、状況によっては餌に集まらないこともあるだろう。それは、そのことによって内部の反応の連鎖の一部が(列車線路のポイントのごとくに)切り変わり、外に現れる反応が異なったものになるのである。
このような、外からの縁や内部の状況に応じて、生得的な内部の縁の仕組みによって自動的に決定されて引き起こされる反応を反射と呼ぶことにする。反射は、条件によって結果の決まった機械的・決定論的な反応である。

少なくとも棘皮動物までの動物は、反射だけで生きており、反射は、人間における内分泌線の働きや膝蓋腱反射のごとく、ただ実行されるのみで、情動も感情も伴わないと想像する。
② クオリア、ホムンクルス、中核意識 (条件反射、学習)
内部の縁の仕組みが高度になり、眼などの感覚器官ができ、中枢神経が発達すると、外からの縁の感知も高度になる。感覚器で実際に縁を受けてから反射によって反応するだけではなく、経験によって、利害に関わる縁に先んずる縁を感知し始める。その結果、利害に関わる縁を先取りし、反応の立ちあがりが早くな る。条件反射である。いってみれば、条件反射とは、フライングしてレースに勝つ仕組みだと言える。
おなじみの池のコイの場合で言えば、手を打つ音の後、餌を食べることを何度か経験すると、手を打つ音だけで餌を取ろうとする反応が引き起こされる。
注意して頂きたいのは、この時、コイは、手を打つ音のカテゴリーに反応しているのであって、そのつどの一回的音を聞いて反応しているのではない。手を打つ音は様々に異なり、一回性のままありのままに聞いていたのでは、共通した反応は起こり得ない。「ありのまま」は条件反射にはかえって邪魔である。ありのままに音を聞くのではなく、カテゴリーにあてはまるかどうかだけが聞き分けられ、あてはまれば反応が引き起こされる。
ダ・ヴィンチ顔負けの絵を描いた自閉症サヴァンのナディアに比して、「健康」で凡庸な幼児の絵はあまりに平板である。(ラマチャンドラン他『脳のなかの幽霊』(角川書店)P249参照)
その理由は、「普通」の幼児は、「足は胴体の下にある棒のようなもの」「顔は丸くて、目と鼻と口がついている」といったレベルの単純なカテゴリーで見ているからだと考える。成長し、経験を積むことによって、カテゴリーは徐々に細分化される。「棒のような足」から、「丸い膝」・「ふっくらとした脹脛」などへと細分化されることで、我々は「ありのまま」に少しずつ近づいていく。
普段、私達は、カテゴリーが生まれる過程は、まず複数の個が収集され、その後それらの共通点が抽出される、と考えがちだ。しかし、実際は、そうではな い。そのつどの現象をそのままに見ることは非常に高度なことであり、人間においてすら、正しい観察の訓練を積んだ上でようやく実現できるか、あるいはできないかもしれないことである。進化の過程においてまず行われるのは、ともかく拙速に利害に関わる現象のカテゴリーが用意され、それに当てはまるかどうかどうかだけを判定し、十把一絡げに同じ反応(条件反射)をすることである。その後、カテゴリーは徐々に精緻化されていくが、それでもカテゴリーであることには変わりはない。(現象を現象のまま「ありのまま」にみることがもし可能だとしたら、それは如来にしかできないことだろう。)
この利害に関わるカテゴリーに対するセンサーであり、ふさわしい反応を起動する仕組み、条件反射を起動する仕組みが、元々のクオリアである。クオリアは、利害に関わる縁をおそらく二、三度経験するだけで形成される。一方、利害にまったく関わらない縁は、何度経験してもクオリアは形成されなかった筈だ(少なくとも、ある程度進化が進むまでは)。
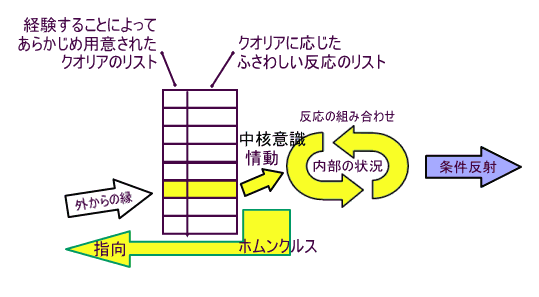
『脳内現象』の末尾近くで、何度かクオリアの「プラトン的完全さ」が言及されている。青の青さ、円の丸さといったクオリアのイデア的性格は、「カテゴリーに反応する仕組み」というクオリアの本性から自然に派生すると思う。
クオリアは、免疫システムに似ている。縁を経験することによって形成され、その後の同カテゴリーの縁への反応を、より適切ですばやいものにする。
クオリアにおいては、最初の経験が大きな影響を残す。例えば、ライバルから尻尾を巻いて逃げることで身の安全を保ったら、その反応が以降の反応になる。 ただし、この連結は固定的ではなく、その後様々な経験を重ねることによって、対応する反応は変化するし、新たなクオリアが生まれたりもする。
現実の世界でさまざまな事物に囲まれていると、しばしばクオリアは競合する。しかし、クオリアには順位があり、上位のものが自動的に起動して、下位のものは働かないので、混乱は生じない。例えば、天敵と獲物の両方に出会った時は、危険を喚起する天敵のクオリアが上位にあり、避難の反応を起こす。しかし、 この順位も身体の内部の状況によって変動する。空腹の度合いが高ければ、獲物のクオリアが天敵のクオリアに勝ることもあるだろう。
クオリアを刺激した縁は、利害に関わるものであるから、動物個体にとって重要である。感覚器のフォーカスは、その縁に集中される。すなわち、指向される。この指向性をホムンクルスと呼びたい。このホムンクルスは、「見渡して、その中から意味を見出す」ような能動的統括的機能ではない。クオリアを通して縁に attract される受動的反応である。クオリアに適合しないものは、利害に関わるものとして経験されたことのないものであり、ホムンクルスを起動しない。見えていても、見ていない。ホムンクルス は、常住して意味あるものを次々と見つけているのではなく、利害に関わる縁がクオリアを喚起したときだけ、その縁に向けてそのつど自動的に立ち上がる指向性の働きである。
言うまでもないことだが、ホムンクルスによって指向された縁は、直接ありのままに見られるのではない。再度クオリアによってカテゴリーの篩にかけられる。
利害に関わる縁は、クオリアを起動し、さらにクオリアによってホムンクルスが起動する。ホムンクルスによって指向された縁は、再びクオリアを喚起する。 クオリアとホムンクルスは循環して起動しあい、「葦の束」のように支えあう。この循環は、別のさらに重要な縁がクオリアを捉えるまで継続し、そのような縁が現れれば、クオリアとホムンクルスの循環は、そちらへ移行する。
本来そのつどの反応であるクオリアとホムンクルスが、このように循環して連鎖していくことが、我々が自分を持続したものとして感じる原因のひとつであろう。
クオリアとホムンクルスに対する私のこの解釈は、あまりに狭く限定的だという批判があるかもしれない。しかし、逆に私は、クオリアやホムンクルスという言葉の通常の使われ方は、多義的で並列的過ぎると思う。進化が進めば、基礎的なクオリア、ホムンクルスを土台にして、さまざまな反応が起こってくる。それ らの高次の反応は、プロセスを追って、基礎的なものとは区別して考えられなければならない。
情動も、進化のこの段階で発生すると考えられる。ヒトデの例で見たように、餌の匂いは、捕食行動のスイッチに生得的に回路が繋がっていた。しかし、手を打つ音はそうではない。本来繋がっていない縁と反応とを接続する仕組みが情動ではないだろうか。手を打つ音がクオリアを通して情動のスイッチを入れ、身体全体が捕食行動のモードになると考える。
ダマシオは、情動とは、対象(私の言葉なら「クオリアを起動した縁」)によって引き起こされる身体の内部状態の変化であり、それは、顔色や血圧の変化などにおいて観察可能(公的)であり、また意識以前のものであり、コントロールできない、としている。(一方、感情はその個体だけの私的なものだとする。) (『無意識の脳 自己意識の脳』(講談社)参照。以下のダマシオの説もすべて同書による。小論集のページでも紹介しています。)
茂木さんは、情動は意識に上らず、感情は意識に上る、としておられる。
私の言う「情動」も、これらとほぼ同じだが、厳密には少し狭く、ヒトデの例のような生得的な反射反応による変化は含めていない。反射は、情動なしに作動できるから、その時点ではまだ情動の反応は始まっていないと推察する。
進化のこの段階に先んじて、中枢神経ができ、身体の状況の不断の感知を始めていた。それはホメオスタシスの維持のため、身体のバランスを統一して自動的に調整する仕組みである。この仕組みによる身体状況の感知をダマシオは「原自己」と 呼んでいる。(自己という名がついているが、勿論自己として意識されているわけではない。意識以前の、意識の前提として必要な仕組みのひとつである。原始的中枢を持つヒトデは、原始的な原自己があったと言っていい。中枢は、本来、身体の状況の不断の感知・調整の仕組みなのだから。)
ホムンクルスによる縁への指向と、クオリアを通じて縁がもたらした原自己の変化とが結びついて、ダマシオの言う中核意識が発生する(詳細は前掲書参照)。中核意識は、過去も未来もまだない「今・ここ」だけの働き、そのつどの意識であり、わたしがホームページで多用してきた表現ではノエシスにあたる。
中核意識は、自己の意識ではない。自己を対象化してとらえたら、それはノエマ自己であってノエシスではない。中核意識は、そのつど縁にむけて働いている働きである。
中核意識は、イメージしにくい。中核意識は、自己についての意識などないまま、そのつど現に働いている意識そのもの、まさに「中核」の意識であるが、我々は「意識」と聞いた途端、自己的ななにかを対象化して考えてしまう。
我々人間の場合で例を挙げよう。スポーツや仕事や遊びに集中して取り組んでいる時。あるいは、座禅中に妄想が沸いて、知らぬ間に次から次へと連想して、 あらぬことを思っている時。あるいは、車を運転中に、なにげなくCDのスイッチを入れ、音楽にあわせてリズムを取りながら、缶コーヒーを一口飲む。あるいは、嫌いな人が歩いてくるのを見つけて、「ゲッ、ヤダな」と思う。
このような、自然ななにげない振る舞いの時働いているのが中核意識である。そして、さらに言えば、我々が、自己を対象化し、反省したり、計画したりする時でも、その働きそのものは中核意識の働きである。しかし、進化のこの段階では、まだ自己を対象化することはできない。それは、もっと先のことであって、 中核意識は、まだ決定論的に反応するだけである。
③ フィードバック
クオリアは、利害に関わる縁に一歩早く感応する仕組みであった。中枢神経がさらに発達すると、それに加えて、反応のアウトプットの精度が上がる仕組みもできあがった。
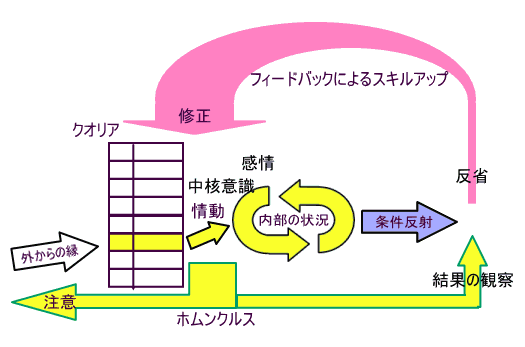
条件反射の結果は、利害に関わる縁への反応の結果であるから、当然個体の利害にかかわり、クオリアを起動する。ホムンクルスが再度起動し、結果の状況が 指向される。望ましい結果が繰り返し得られていれば一連の反応は強化され、芳しくない結果が続けば反応のパターンは修正される。このようにして、反応は、 熟達の度を加える。
具体的には、牧羊犬のようなケースをイメージしている。
この時点では、まだ自覚的な反省が行われているわけではないだろう。中核意識は、取りたいものを取ろうとし、逃れたいものから逃れようとする。純粋にそ れだけであって、反省や分析はなされていない。しかし、なんらかのフィードバックが無自覚の内に自動的に行われて、反応がスキル・アップされていく。
ワーキング・メモリが、ある程度発達して、なんらかの役割を果たしているのかもしれない。
念を押しておきたいのは、この段階にいたるまでの反応は、すべて定められたレールの上の反応であった。反応の立ちあがりを早めたり、反応をより精緻にすることはあっても、決定論的な反応であった。「ああしようか、こうしようか」という主体性は、まだない。それが可能になるのは、ようやく次の段階である。
④ 主体性の発現
この段階が、我々人間、成人のレベルだ。仏教的に言えば、凡夫のあり方という事もできる。
この段階で進化は爆発的に展開する。さまざまな能力がほとんど同時にスタートし、それらは絡まり合い互いに利用しあって進展のペースは飛躍的に上がった。単線的な言葉でひとつずつ文章化していくにはどうすればいいのか、大変難しい。
思いつくまま順不同で列挙だけしておこう。
道具の使用・製作。分業。段取り(目的と手段の重層化)。社会・文化の発展。しつけ・教育。言語。…
クオリアの変化についても一言付け加えておきたい。
かつては、利害に関わる縁は、餌や天敵や異性や避難場所など、そんなには多くなく、それに対応するクオリアも、同様に多くはなかっただろう。しかし、人 類になって上記のような出来事が起こると、利害に関わる縁の種類は、爆発的に増加した。後で触れるような縁の吟味・検証も行われ、クオリアには部分の微妙 な差を感じとる識別性能も必要になった。この結果、クオリアは、利害のカテゴリーに1:1で対応するのではなく、ひとつのカテゴリーをいくつかの特徴に分 解していくつかの汎用性あるクオリアの組み合わせで捉えることが始まった。部品的クオリアと呼んでおこう。部品的クオリアとは、「青の青ら しさ」とか、「すべすべした手触り」とか、我々がクオリアを議論する時に、もっともクオリアらしいクオリアと捉えがちなものである。しかし、これは、本来 のクオリアの姿ではなく、二次的に派生した「高度な」クオリアの形だと思う。
人間(成人)においては、クオリアとカテゴリーと言葉とは、三位一体の関係だ。基本的なものであれ、高度に発展したものであれ、クオリアがあれば、相当するカテゴリーと言葉がある。逆に、言葉があれば、クオリアとカテゴリーがある筈である。
今私の住んでいる信州伊那谷には「みやましい」という方言がある。「よく働き、しかも仕事の処理能力も高い」といった意味だろうと思うが、どうもそういう即物的な意味に収まらない豊かなニュアンスがあるらしい。大変な誉め言葉だという。よそから来た私は、「**さんは、ホンにみやましい」と聞いてもピンとこないし、この言葉を使うこともない。私には、「みやましい」のクオリアはないのだ。
ひとつの言葉を聞くと、長期記憶の中から関連する記憶が立ち上がり、豊かなイメージを喚起する。例えば、「休日の朝」と聞くと、私は、コーヒーの香りや 読みかけの新聞や窓辺に差す木漏れ日やバロック音楽をイメージする。(こんな休日の朝を過ごしている訳でありません。ただ勝手に湧いてくるイメージで す。)このような言葉によって喚起される豊かな具体的イメージの重なりもクオリアと呼ばれることがある。これも二次的で高度なクオリアであろう。
クオリアは、元々の「利害に関わる現象にカテゴリーで感知して反応する仕組み」から発展し、イデア的クオリア、部品的クオリア、豊穣なるイメージのクオリアなどに展開した。(イデア的クオリアと部品的クオリアは、≒かもしれない。)こうした多様な「クオリア」を区別せず一挙に扱おうとしている点に、クオ リアついての議論の分かりにくさの原因があるのではないかと思う。
様々な展開の内、特に重要なものをあげるなら、長期記憶の仕組みができたことであろう。長期記憶によって、中核意識は過去の経験を指向し直し、過去の経験を新しいクオリアにかけることができるようになった。それによって可能となったことは、条件反射とは質的にまったく異なることだ。
成人のそのつどの反応の流れにそって、考えてみよう。
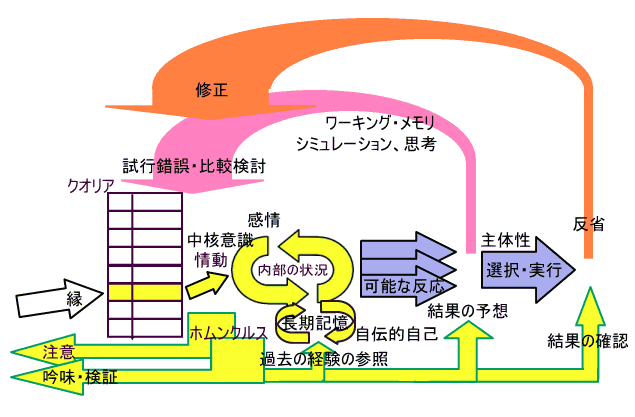
利害に関わる縁と出会う。縁はあてはまるクオリアを喚起して、情動がふさわしい反応を身体に起こす。その一環として、ホムンクルスは、その縁を指向する。指向された縁と情動による原自己の変化とが連結して中核意識が立ちあがる(ダマシオ前掲書)。クオリアに起動されたふさわしい反応のパターンは、内部の反応の仕組みによって処理・実行されていく。ここまでは同じだが、ここからが異なる。この過程において長期記憶のなかから関連した記憶が自動的に浮上してくる。(どの記憶がどのように選択されて浮上するのかは、謎だ。ひらめきの神秘の鍵は、おそらくここにある。【04,12,23,加筆 A・Hさんとの意見交換で、人間に主体的努力が可能であるためには、なんらかの仕方で決定論が超えられなければならず、そのためにはどこかで量子的な不確定性が働いていなければならないのではないか、と思い至った。もしそうだとすると、この長期記憶の浮上の仕組みが、一番可能性が高そうな気がする。)この記憶も内部の縁に加わり、内部の反応の連鎖が続き、ひとつの選択肢が可能な反応としてワーキング・メモリのテーブルに上がる。テーブルの上の選択肢は、 ホムンクルスを attract し、再びそれに応じたクオリアが起動する。同様のサイクルが繰り返され、ホムンクルスは繰り返し縁を指向し、縁は吟味・検証される。また記憶それ自体が ワーキングテーブルに昇って、ホムンクルスに指向され、クオリアを起動することもある。元々の縁と記憶からのいくつもの縁とが撚り合さり、回路を回るたび に選択肢が紡ぎ出され、ワーキング・メモリ上でそれらが比較検討される。このようなシミュレーションが思考だ。そしてついに、時には合理的に、時には感情によって、ひとつが選択され実行される。
クオリアを起動する縁は、従来は外からの縁だけだったが、長期記憶の仕組みができて、記憶(つまり内部の縁である)がクオリアを起動することもでてきた。
外の環境の安定度が高いと、外からの縁より記憶の方がクオリアを起動する頻度が高くなる。記憶は、元々一度クオリアを起動したものであり、気になること、気に入っていることが蓄積されているからである。記憶(内部の縁)を過大に評価すると、唯識的な考えが生まれる。
複数の可能な反応をシミュレーションして比較・検討することで、ついに外部・内部の縁によって決められたのではない反応が可能になった。生命が生まれて 40億年近いというが、そのほとんどを生命は決められた一本のレールの上をひたすら懸命に歩いてきた。やってきたことはただ、より早く、より正確に、ということでしかなかった。それがようやく、人類、あるいはその直前あたりから、反応に選択肢を持ち、その内からどれかを選ぶことが可能になった。道は単線で はなくなり、いくらかの巾が出来た。その巾の中で新たな経験をすることで、新たなクオリアと新たな長期記憶を積み上げ、その相乗効果で反応の巾をさらに広げられるようになった。このことを主体性の発現だと言っていいと思う。
④ⅰ 凡夫
とはいえ、せっかくの主体性は、うまく生かされているのだろうか? 凡夫においては、せっかくの主体性も、苦を拡大することにしか使われていないのではないだろうか。凡夫の反応を検証してみよう。
そもそも、生命とは、反応を持続させ、発展させようとする反応であった。生命のこの本性は、クオリアに反映されており、クオリアは、生命個体の維持・発展にかかわる利害に反応する仕組みであった。進化を極めた人類といえど、その点はかわることはない。
さらに、凡夫においては、生命の根本的傾向に加えて、様々な進化の「成果」が我執を強力にしている。中核意識生成のもととなった原自己(ダマシオ前掲書)は、反応の場としての身体の持続性を反映して、我常住感の基底をつくる。身体はホムンクルスの指向性の矢に出発点の一貫性を与え、出発点に我を妄想させる。クオリアとホムンクルスの循環・連鎖(②を参照)が、中核意識に一定の持続性をもたらし、長期記憶を指向した中核意識は、そのつどの一貫性ある自己観(自伝的自己。ダマシオ前掲書)を編集する。このように何重にも塗り固められて「我」の張子(ノエマ自己、アートマン)は、巨大で立派な見かけを獲得 し、守り育てるべきものとして担ぎ上げられる。
自伝的自己は、そのつど中核意識によって紡ぎ出される。「つど」が違えば、自伝的自己も異なる。つまり「自伝」はそのつど書きかえられる。しかし、そのつどの自伝的自己には整合性・一貫性があるので、「我」は一貫性あるものとして想定される。
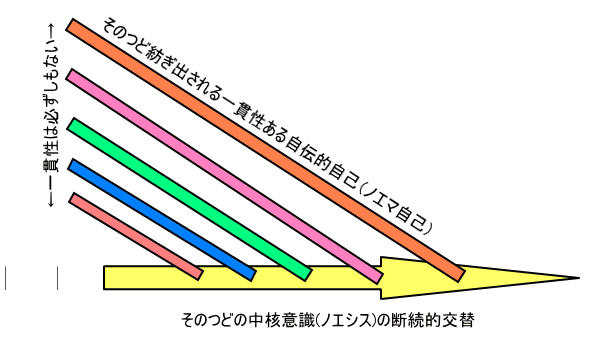
かつて生命の反応は、そとつどそのつど縁に対応して自分を守り育てようとするものだった。そのつどの単発的反応の連続に過ぎなかった。
しかし、一貫して存在する「我」があると妄想することで、自分を守り育てようとする反応は、長期的計画を持ち大規模になり、用意周到なものになる。
とはいえ、しょせんは凡夫である。一貫して存在すると妄想された「我」という象徴に生命の本性的我執が収斂しただけのことで、どれほど長期的計画的用意周到であれ、よく検討された究極目的があるわけではない。究極目的なしに、ただ手段だけが積み上げられる。なぜ自分を守り育てようとするのか、という問いはけして問われず、ただ用意周到に(しばしば臆病に)「我」を守り育てようとする。
未来の自分を守るために、あらゆる努力が払われる。学歴、出世、名声、地位、資格、権力者とのパイプづくり、媚びへつらうこと、誰かを蹴落とすこと、自分を飾り嘘をつくこと、戦う前に戦いを降りて負けて傷つくことを避けること、ブランド品を身につけること、時には卑屈な、時には横柄な応対が無自覚のまま 自動的になされる。このように自分を苦しめ、人を苦しめ、互いに苦しめ合いながら、今日を犠牲にして明日に備える。毎日を明日のために犠牲にして、安んずることなく、やがて一生を終える。
時には、もっと悲惨なことも起こる。
たとえば「**の連中は、(自分たちに対して)良からぬことを企んでいる(自分たちにとって)危険なやつらだ」という噂を耳にすると、たちまちそのようなクオリアが用意され、それまで互いに普通に混ざり合って生活していた**の人々に対しても、それに「ふさわしい」反応が起動される。「そういえば、あの時あんなことがあった。あいつらのおかげで、私達の大切なXXは害されたんだ。昔からあいつらはそうだったんだ。」新しいクオリアで過去は再評価され、反感は、反感を呼び、憎しみは憎しみを喚起し、民族や宗教間の対立・紛争は、平和な時には想像もつかないほど容易く燃え上がる。そして主体的努力や、シミュレーションによって最適な反応を検討する能力は、攻撃・報復のために総動員される。憎悪と犠牲は、ますます拡大再生産される。
**に何を代入しますか? **教徒、北朝鮮、ユダヤ人、ホワイトハウス、ネオコン、霞ヶ関、**党、労働組合、資本家、ホームレス、フリーター、……
「日本人」を代入する人もいるだろう。仏教徒こそ敵だ!と叫ぶ人も、今は稀でもそのうち増えるかもしれない。
**に攻撃されるかもしれないという心当たり(やましさ)のある人ほど、おそらくこの反応は起こりやすい。
このように考えると、進化の結果やっとせっかく手に入れた能力も、実はかえって苦を増やすことに使われているのではないだろうか。自分を守り育てるための進化が、かえって苦を生んでいる。人間の能力は、いってみればマンモスの牙の如き過剰進化で、我執を増強し、実は自分を苦しめているのではないだろうか?
しかし、凡夫といえど、疑問に思うことなくただ苦しみ、苦しめあっている訳ではない。「なんのためにこんなことをしなくてはいけないのだ?」しばしば自分のあり方が反省・検討のサイクルにかけられ、自動的盲目的反応に疑問を抱く。「俺はあれこれ計画しこんなに懸命に頑張っているけれど、一体なんのためなんだ?」無反省に取り組んできた中期的目的が自問される。(長期的 or 究極の目的は、もともとないのだ。)しかし、この疑問は、相変らず我執を原動力にしている。「どうして俺はこんなにつらい思いをしなくてはならないのか?」我執によって我執による苦を処理しようとしても、うまくいくはずはない。しかし、それでも、この疑問は我執への疑問の第一歩であり、宗教的発心につながる種である。苦を自覚せぬまま、苦しめ続け、苦しみ続ける人は多いのだ。苦に気づくことは、大切な第一歩である。
④ⅱ 仏弟子
仏教は、苦に対処する教えだ。釈尊は、苦の原因を追求され、それに対処する方法を発見された。守り育てる「我」があると妄想し、それに執着して、無自覚な自動的反応を繰り返し、苦を作り出している。無常=無我=縁起を知って、執着を止め、苦を作り出すことを止めよ。
仏教の苦への対処は、苦を逃れることではなく、苦を作らないことである。
仏教は、生命の本性、自分を守り育てようとすること、を超えようとする。仏教は、生命であることを超越せんとする挑戦なのだ。
では、具体的に仏教はどういう方法を教えているのか。それが一番端的に説かれているのは、念住経(SatipaTTAna-sutta)であろう。ヴィパッサナー(毘鉢舎那、「止観」のうちの「観」)でもっとも重視されている経だ。詳しくは、例えば、片山一良訳『パーリ仏典 中部 根本五十経篇Ⅰ』(大蔵出版)P164~などを是非参照して頂きたい。(片山訳では、経題は「念処経」となっている。)ここに説かれているのは、いわゆる四念住(四念処)である。四とは、身と受と心と法であり、それらを「観つづけて住む」ことが説かれている。参考のため身髄観から正知の部と法の髄観から蓋の部だけを引いておこう。(上記、片山訳による)
身髄観 正知の部
つぎにまた、比丘たちよ、比丘は、進むにも退くにも、正知をもって行動します。真直ぐ見るにもあちこち見るにも、正知をもって行動します。曲げるにも伸 ばすにも、正知をもって行動します。大衣と鉢衣を持つにも、正知をもって行動します。食べるにも飲むにも噛むにも味わうにも、正知をもって行動します。大 便・小便をするにも、正知をもって行動します。行くにも立つにも坐るにも眠るにも目覚めるにも語るにも黙するにも、正知をもって行動します。
以上のように、内の身において身を観つづけて住み、あるいは、外の身において身を観つづけて住み、あるいは、内と外の身において身を観つづけて住みます。また、身において生起の法を観つづけて住み、あるいは、身において滅尽の法を観つづけて住み、あるいは、身において生起と滅尽の法を観つづけて住みます。そこで、かれに<身のみがある>との念が現前しますが、それこそは智のため念のためになります。かれは、依存することなく住み、世のいかなるものにも 執着することがありません。
このようにまた、比丘たちよ、比丘は身において身を観つづけて住むのです。法の髄観 蓋の部
ではまた、比丘たちよ、どのようにして比丘は、もろもろの法において、法を観つづけて住むのか。比丘たちよ、ここに比丘は、五蓋の法において法を観つづけて住みます。では、比丘たちよ、どのようにして比丘は、五蓋の法において法を観つづけて住むのか。比丘たちよ、ここに比丘は、内に欲貪があれば<私の内 に欲貪がある>と知ります。あるいは、内に欲貪がなければ、<私の内に欲貪がない>と知ります。また、未だ生じていない欲貪がどのように生じるかを知ります。また、既に生じている欲貪がどのように断たれるかを知ります。また、断たれている欲貪が将来どのようにして生じないかを知ります。
あるいはまた、内に沈鬱と眠気があれば<私の内に沈鬱と眠気がある>と知ります。あるいは、内に沈鬱と眠気がなければ<私の内に沈鬱と眠気がない>と知ります。また、未だ生じていない沈鬱と眠気がどのように生じるかを知ります。また、既に生じている沈鬱と眠気がどのように断たれるかを知ります。また、断たれている沈鬱と眠気が将来どのように生じないかを知ります。
あるいはまた、内に浮つきと後悔があれば<私の内に浮つきと後悔がある>と知ります。あるいは、内に浮つきと後悔がなければ<私の内に浮つきと後悔がない>と知ります。また、未だ生じていない浮つきと後悔がどのように生じるかを知ります。また、既に生じている浮つきと後悔がどのように断たれるかを知りま す。また、断たれている浮つきと後悔が将来どのように生じないかを知ります。
あるいはまた、内に疑いがあれば<私の内に疑いがある>と知ります。あるいは、内に疑いがなければ<私の内に疑いがない>と知ります。また、未だ生じていない疑いがどのように生じるかを知ります。また、既に生じている疑いがどのように断たれるかを知ります。また、断たれている疑いが将来どのように生じないかを知ります。
以上のように、内の法においてもろもろの法を観つづけて住み、あるいは、外の法においてもろもろの法を観つづけて住み、あるいは、内と外のもろもろの法において法を観つづけて住みます。また、もろもろの法において生起の法を観つづけて住み、あるいは、もろもろの法において滅尽の法を観つづけて住み、あるいは、もろもろの法において生起と滅尽の法を観つづけて住みます。そこで、かれに<法のみがある>との念が現前しますが、それこそは智のため念のためになります。かれは、依存することなく住み、世のいかなるものにも執着することがありません。
このようにまた、比丘たちよ、比丘はもろもろの法において法を観つづけて住むのです。
細かなことは置いておけば、ここに説かれていることは、自己観察である。そのつどそのつどの自分をリアルタイムで(後からの反省ではなく)観察する。
この小論の流れで言えば、そのときそのときの自分という反応の組み合わせの一部分にホムンクルスの指向性を向けること。指向したものを、仏教で学んだクオリアにかけること。
クオリア、ホムンクルスをはじめ、長期記憶やシミュレーションや、その他一切の能力は、生命が自分を守り育てるために開発し磨きをかけてきたものだ。仏教は、その能力を逆用して、「守り育てるべき自分はない」と見定めよ、と教える。進化の結果得た能力は、過剰進化であり、我々を苦しめるものであったのだが、仏教は、その過剰進化の成果を今度は逆向きに使って、今の自分の反応ぶりを観察し、分析せよという。そして、ありもしない自分を守り育てようとしてい る無明に気づきなさい、それが苦を創り出す原因である、と教える。これが仏教である。
この観察・分析は、経にもあるとおり、食事や大小便その他すべての日常生活において途切れることなく継続されるよう努められねばならない。
このような不断の自己観察の努力によってふたつの成果がもたらされると思う。
第一に、「戒」。自分が自然のままに執着の反応として苦を作っていることにそのつど気づくことができ、その反応にブレーキがかかる。ありのままであれば、得だ損だ、勝った負けたと、はしゃぎまわり、落ち込んだり、妬んだり、恨んだり、怒ったり、状態は激しく変化し、とても修行に集中することはできない。戒によって、自分の反応の状態を修行にふさわしい静謐なものにしていくことができる。
もうひとつは、自己観察はそのまま、自分が縁に反応して起こる無常にして無我なる現象であることを見ることであるという点である。すなわち、仏教=無常=無我=縁起を自分という反応において確かめることになる。
しかし、特に後者は、なまやさしくはない。理屈・戯論のレベルで理解できても、自分のこととして腹に落ちて納得することはむずかしい。ちょうど、誰でも いつか死ぬことは分かっていても、自分が現に今刻々と死につつあることはなかなか実感できないように。生命が、意識の誕生するずっと以前から、四十億年をかけて蓄積してきた自分を守り育てる仕組みを書き換えることは、容易ではない。
無常=無我=縁起を自分のこととしてなかなか見ることができない理由の一つは、通常の見方では、ホムンクルスが指向したものを、我々はクオリアによってしか見ていないからであろう。クオリアは、カテゴリーで現象を掬いとっているにすぎない。カテゴリーは本質的に無時間的であり、現象は常住の存在として捉えられてしまう。
カテゴリー化をせず、現象を無常=無我=縁起のまま観る練習として仏教が開発したのが、止観(シャマタとヴィパッサナー)だと思う。法蔵館『仏教学辞典』によれば、「もろもろのおもいを止めて心を一つの対象にそそぎ(止)、それによって正しい知慧を起こして対象を観る(観)こと」とある。私の言葉で言い換えるなら、例えば呼吸なら呼吸だけに集中し、静謐な状態で、生々しい実感によって現今の呼吸を詳細に持続的に感じ続けることだ。これによって、確かに定は深めることができる。別の言い方をすれば、定における自己観察によって自分の無常=無我=縁起を観ることが、仏教の方法である。
止観とは、対象となる現象(自分という現象のある部分、例えば呼吸など)をホムンクルスで指向し、クオリアによらず、実感でそれを集中的に感じ続けることだと思う。
ブッダダーサ比丘の言う、無念無想の「深すぎて役に立たない定」(小論集「Handbook for Mankind」参照)とは、ホムンクルスの停止した状態ではないかと思う。外の縁も、内の長期記憶も指向されていない状態である。(かつて私は、「主客未分」を言い、「主客対消滅」に訂正し、さらに「意識の指向性停止体験」と言い換えたが、この最後の表現は言葉としてはいいところを突いていたように思 う。仏教の方法としては、主客未分などと同様に「役に立たない」のであるが。)
ホムンクルスが停止した定においては、クオリアを起動する縁はなく、原自己に変化は起こらず、中核意識は生成されない。私という現象は起こっておらず、 だから無我を観ることもできない。縁によって起こっている無我なる現象が、自分は無常にして無我なる縁起の現象だと知ることが、無我を知ることである。
日常生活における不断の自己観察・自己分析と止観と、両方の自己観察が必要だと考える。
④ⅲ 仏 如来
では、この小論の流れに沿って、仏とはどのようなあり方であるのか、すこしだけ想像してみよう。私のような凡夫の極みがまったくもっておこがましい冒険であるが、理論上の想像としてお許し頂きたい。
まず、問題のクオリアであるが、クオリアの仕組みについては、仏といえど維持されていると考える。クオリアがなければ、日常生活に不便をきたすであろうし、弟子と会話することも不可能だろう(言葉は、カテゴリーに対応するものだ)。では、現象にカテゴリーとして接しているのであって、ありのままに現象を 見ていないのか? この点は、よく分からない。おそらく現象のままに見ることもカテゴリーの篩にかけることも両方が可能なのだろうと思う。
勿論ホムンクルスの働きも維持されている。長期記憶もシミュレーションの働きも当然ある。
では、仏は、何が一番凡夫と違うのか?
「自分にとっての利害」という要素が、まったく抜け去っているのだと思う。損した、得したと、うろたえたり、はしゃいだりすることはない。怒ったり、妬んだり、恨んだりすることはない。そのような第二の矢はもはや受けず、第一の矢は縁起によることとして受け入れる。穏やかに平安であり、思い煩うことなく 軽安である。
利害なく有情を見て、しかも、ありのままに見るので、有情のあり様がよく分かる。それは、ありもしない自分を守り育てようと執着して、自分を苦しめ、人を苦しめ、互いに苦しめあっている凡夫のあり方である。すべての現象は、縁起によってつながっていることも見える。どこまでが自分でどこからは他という感覚はもはやない。共に縁起しながら、無用に苦を作り、苦しんでいる有情への慈悲が発動する。我執に代わって、慈悲が自動的反応を導くものとなっている。
これが如来という現象だと思う。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
穴だらけの稚拙な思いつきの仮説です。ご批判をお願いするほどの完成度はありませんが、発展の種が潜んでいるような気もします。もし、お気づきの点があれば、助言を頂ければ幸甚です。
2004年7月26日 曽我逸郎


