旧サイトから転載
2007年3月18日
昨年の秋東京へ出た折に買いだめしていた本を、何冊か読んだ。
①『ジャン・ピアジェ』白井桂一編著、西田書店
学としての体系が大きすぎて、集中度の落ちている私には手に余り、ところどころつまみ食いをしただけで投げ出してしまった。人の個体発生(成長)の過程で「我」がいかにして妄想されるに至るか、興味があるのだが、いずれまたあらためて取り組みたい。我執が生まれてくる展開を、系統発生(進化)やそのつどの反応のプロセスにおけると同様に、一人の人間の成長の道筋の上でも跡づけることができれば、たくさんの発見がありそうに思える。今後の課題。
②『脳はなぜ「心」を作ったのか-「私」の謎を解く受動意識仮説』前野隆司、筑摩書房
sincekeさんからのメールで05年4月にお勧めいただいていた本。ようやく読めた。私の考えと重なる点も多く、おもしろかった。特に P172 あたりの記述は、私の考える無我に、理屈の上ではもうほとんど手が届いている。全体を貫く「受動意識」という考えも、「縁によって起こされる」という釈尊の教えに近い捉え方だと思う。ただ、楽観的かつ大胆ではしょりすぎの部分もあり、もう少し丁寧に詰めてもらいたいと感じるところもあった。<「私」の謎> が錯覚として片付けられていて、おそらくはそのとおりであろうが、その錯覚がどのようにして生じるのか、もう少し詳しく論じてもらいたかった。
③『赤を見る 感覚の進化と意識の存在理由』ニコラス・ハンフリー 柴田裕之訳 紀伊国屋書店
装丁がおしゃれで、軽い読み物かと思ったら、学問的な裏打ちのしっかりした侮れない内容で、こちらもおもしろかった。
137,8 ページで<経験をする主体があって初めて経験が存在し得る>(先に我あり)という考えに対するアンチテーゼとして、<経験があって初めて経験をする主体が存在し得る>という考えが提示されている。これは、無常=無我=縁起に接近する一歩だと思う。この分野の科学は、釈尊のお考えに2500年遅れて一歩ずつ近づきつつあるように思える。
意地悪な方は、「曽我は聞きかじりの科学をあてはめて釈尊の教えを自分勝手に読んでいるからそういう錯覚を抱くのだ」と思われるかもしれない。しかし、 私としては、無常=無我=縁起を神秘化せずに言葉どおりに解釈すれば、科学が行き着こうとするところを先取りするものであると思う。
また、どうして曽我は仏教の範囲を逸脱してしつこく科学的な話題を取り上げるのかと、いぶかしく感じておられる方もおられよう。その理由は、まず釈尊の教えと科学を突き合わせることで、釈尊の教えへの新たな視点が得られ、より深く考えることができるからだ。そして、もうひとつ理由がある。無常=無我=縁起が、宗教の枠を超えて、人類共通の世界観、否、自己観として広まることを祈っているからだ。無常=無我=縁起がパラダイムとして広まれば、執着や憎悪は、根絶はとても無理でも少しは勢いを削がれるだろう。そうすれば、世界を覆う苦も、僅かでも減らせるに違いない。釈尊も、宗教を起こし祖になろうとされた訳ではない筈だ。無常=無我=縁起の教えによって、世の苦を減じることを目指された。であるなら、どういう方便であれ、無常=無我=縁起を世に問いかけることは、釈尊のお考えに適うことだと思う。
***
さて、この小論は、はじめは『受動意識仮説』の感想を書こうと思ったのだが、『赤を見る』も読み始めてしまったこともあり、さまざまな視点や着想が錯綜してしまった。どれかの本の感想という形はあきらめて、新たに学んだことを、ノエシスやクオリアや「いつも化」といった言葉でこれまで自分なりに考えてきたことといっしょにして、もう一度こねあわせてみたい。釈尊の教えの核心は無常=無我=縁起だと考える私の解釈を、読みかじりながら科学的な視点で再度検 討したい。
この小論の前提となっている考えは、小論《クオリアについて》ならびに《クオリアとホムンクルスを仏教(無我=縁起)の視点から考える》を参照。
◆1 生命であること
『受動意識仮説』では、何度も「こびとたち」という言葉が登場する。複数形であることから分かるとおり、これは脳科学でしばしば冷笑的に言及されるホムンクルスのことではない。そのつどそのつどの刺激(縁)を自動的に処理してくれているサブシステムのことだ。いや、サブシステムというと、メインシステム があるかのように聞こえる。メインシステムと呼ぶに値するものがあるとすれば、それこそホムンクルスであり、アートマンであろう。しかし、そんなものは、 無い(無我)。たくさんの小さな自動的反応が連鎖し撚り合わさって起こる反応。それが、私たち自身を含むすべての生命のあり方だ。
脳科学におけるホムンクルスとは、元々は「私」の中にいる「本当の私」のこと。ガンダムのパイロットのようなものである。意識をホムンクルスによって説明しようとするなら、そのホムンクルスの中にもさらに小さなホムンクルスを想定せざるを得ず、次々と無限により小さなホムンクルスが必要になってしまう。従って、解決にはならないので、ダメな説明である。操縦者として想定される場合のみならず、デカルト劇場(感覚器官から届く情報)を見ているだけであっても、観察者を想定すれば、それは既にホムンクルスである。その意味で、同書P103のイラストは、おそらくは分かりやすさを重視したためであろうが、ホムンクルス的であり、注意深さに欠ける。
念のため書き添えると、小論《クオリアとホムンクルスを仏教(無我=縁起)の視点から考える》では、ホムンクルスという言葉に自分勝手な意味を与えたが、この小論では、上記の普通の意味で使っている。
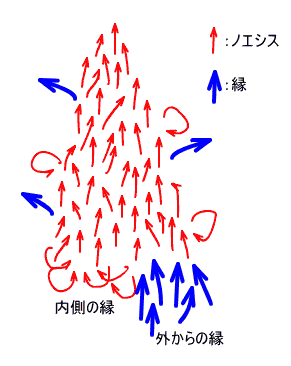
右の図の「内側の縁」というのは、たとえば血糖値とかその時々のさまざまな身体の状態のことであり、「外からの縁」というのは、たとえば外気温や獲物の においなど、その時その時の外の状況・刺激である。それら内外の縁が、それらに応じたさまざまな反応(赤い矢印)を起動する。それらの反応が縁になって、さらにさまざまな反応を起動する。それら反応は、重なり合い、もつれあい、捩れあい、全体として「わたし」という反応となる。比喩的に言えば、次々と水が湧き出してくる泉、あるいは公園の水飲み場のようなイメージだ。
同時にこの反応のまとまりは、内へも外へも縁となって状況に変化をもたらす。例えば、摂食すれば血糖値があがり、外にあった餌は消費されてなくなる。
これらのひとつひとつの小さな矢印も、さまざまなレベルの矢印の集まりも、すべてノエシスと呼ぶべきだろう。以前の私はもっと高次な反応をノエシスとし てイメージしていたが、どこからがノエシスでどこまではノエシスでないか、線を引くことは難しいし、また意味もない。我々のあらゆる反応を総称してノエシ スとして捉えるべきだと思う。
私の言うノエシスは、現象学でいう本来の意味からかなり拡張している。対象化され実体視された自分(ノエマ自己、我、アートマン)に対する、「そのつどの働き・反応としての私」をノエシスと考えている。
ノエシスの働きぶりを納得したければ、簡単だ。例えば、暑いとき自然に汗が出るし、それを止めることもできない。「緊張するな」といくら自分に言い聞かせても、緊張する時には緊張する。あるいは、盲点の実験もおもしろい。(旧サイトのmasayuさんとの意見交換 05,3,2, 参照。)座禅をしてみるのもいい。息の観察に集中しようとどれだけ固く誓っても、たちまち妄想が勝手に湧いて出てきて、気がつけば愚にもつかないことを延々と紡ぎだしている自分に気づく。
生命とは、ノエシス(反応)の組み合わせであり、構成するそれぞれの反応が、反応の組み合わせを維持拡大するように自動的に働きあう、そのような反応の組み合わせだ。外側と内側の状況(縁)によって、それに対応した反応が起動され、その結果適当にバランスが調整され(ホメオスタシスの維持)、生命活動は維持拡大される。
このような自動的反応の組み合わせであることは、我々にも、バクテリアのような単純・原始的な生命にもあてはまる。ジョージ・ブッシュやチェイニーやそのまわりに寄り集まる人々の振舞いも、そうした自然な自動的反応の寄り集まりである。言い換えれば、天然自然のあるがままの欲望の反応だ。バクテリアの時代以前から40億年近く引き摺ってきた自己維持・自己拡大の反応の発露だ。そのことが分かれば、怒りに震えることもなくなる。そのかわりに、暗澹たる、悲しくやるせない、なかばあきらめに近い気持ちになるが…。
この感情は、悲であり、捨であろう。そして、賢しいつもりの彼らが、欲のままに操られ振る舞っている愚かさにいつか気づくように、と祈るなら、慈ともなろう。
◆2 意識=「気づくこと」? クオリアを手がかりに
しかし、上に述べたことで、釈尊の無常=無我=縁起の教えの全体が言い換えられたわけでは勿論ない。釈尊は、生命一般にではなく、人間に教えを説かれたのであり、人間には、生命一般にはない特徴がある。それは、意識だ。
しかし、意識という言葉は、人によって、場合によって、意味内容が様々である。そのことが、意識に関する議論を混乱させている。はじめに、意識をどう定義するか、検討する必要があろう。
まず、「意識的に」という言い方から連想して、意識の定義として「意図を持つこと」が思い浮かぶ。
しかし、ベンジャミン・リベットの実験で明白になったように、人が何かをしようと「意図」する前に、既にその行動は「こびとたち」(ノエシス)によって起動されている。すなわち、先に行動のメカニズムはノエシスを始動させており、その後、後付で「意図」が起こっている。前野氏の言うとおり、空間で起こるのと同様に時間においても辻褄あわせの錯覚(これもまた「こびとたち」=ノエシス)が働き、都合よく順序が入れ替えられた結果、「まず意図があり、その結果行動した」かのごとく感じている。
「意図」は、錯覚なのだ。自由意志は幻想に過ぎない。我々は無我なる縁起の現象であり、縁なくして(すなわち「我」を第一原因として)、何かを開始することなどあり得ない。
「意図を持つこと」はあきらめて、他の候補を検討しよう。
次に思い浮かぶ意識の定義は、「気づくこと」だ。英語の consciousness も awareness も「気づいていること」である。「意図」にしても、錯覚であるなら、「実際とは異なる気づき」であり、広義の「気づくこと」に含まれると考えられる。
しかし、「気づくこと」であるなら、誰(or 何)が気づくのか。意識か? しかし、それでは、「意識とは意識が意識すること」になってしまうのではないか?
このような無内容なウロボロス的トートロジーが思い浮かんでしまう理由は、おそらく、言葉以前から我々に染み付いている、実体視というものの見方の悪癖が、言語に反映されているせいだ。我々は、何かがまずあらかじめ存在していて、それが何かをする( or どうにかなる)、と思い込んでいる。述語(今の場合「気づくこと」)を聞くと、すぐさまその主語を問う。しかし、述語(どういう形であれ「反応すること」)に主語は本来必要ない。
例えば、イソギンチャクが身体のどこかを齧られて身をすくめる場合を考えてみよう。イソギンチャクは、散在神経系で、中枢神経はない。神経は、刺激の伝達しかできない。齧られた刺激(縁)は、散在神経を伝わって、直接筋肉を収縮させる。縁によって反応が起こるだけであって、そこに主語・主体はない。人間の場合でも、熱いものを触った際の脊髄反射反応(これもノエシス)は、熱さの刺激が神経を伝わり、機械的に腕の筋肉を収縮させ、熱さを感じるよりも前に手が引っ込む。縁起による一連の自動的反応であって、どこにも主体は存在しない(無我)。
筋肉の収縮と同じように、「気づくこと」も現象であり、反応なのだ。主体はない(無我)。「わたし」が妄想されることも、現象であり、反応だ。
勿論、こんな主張だけでは、誰も納得してくれないだろう。私自身、説得力があるとは思っていない。誰より、自分自身が納得できる説明が必要だ。糸口を見つけるために、「気づくこと」についてもう少し試行錯誤してみよう。
◆2 ⅰ クオリア
小論《クオリアとホムンクルスを仏教(無我=縁起)の視点から考える》において、クオリアについて一般的ではない定義をした。実を言うと、この定義は結構いいところをついているのではないか、と自負している。もう一度示そう。
「クオリアとは、免疫と同様に、なにかを経験することによって形成され、それ以後それと同類の縁に接するとふさわしい反応(条件反射)を自動的に起動するシステムである。」
この定義は、我々進化した人間が、例えば赤いものを見るときのクオリア、「赤い感覚、赤の赤らしさ」を思い浮かべると、まったくふさわしくないように思えるかもしれない。しかし、私は、もともとのクオリアは、条件反射を可能にする仕組みとして始まった、と考えている。そう考えると、我々人間における発達したクオリアの諸特性も納得しやすい。この一見奇妙な定義を仮に受け入れていただいて、しばらくお付き合いいただき、妥当かどうかご検討いただきたい。
条件反射は、その動物の利害にかかわることにしか形成されない。「利害にかかわる」をダマシオに倣って言い換えれば、「情動を引き起こす」ということだ。なにかの縁(刺激)と特定の情動が結びつけば、条件反射が形成される。
(情動とは、簡単に言うと、身体の状態の変化のこと。小論《ダマシオ 「無意識の脳 自己意識の脳」 を読んで》を参照。)
手を叩く音を聞くと、池のコイは、摂餌行動のスイッチが入る。コイがたくさんいる池なら、情動には競い合って殺到する興奮も加わる。餌が来る前に摂餌行動を開始するわけで、条件反射とは、いうなればフライングによって状況にいち早く対応する仕組みである。この条件反射を可能にしているのがクオリアだ。手を打つ音と摂餌の情動は、本来はまったく関係ない。それどころか、手を打つ音は警戒すべきものであろう。それが手を打つ音のクオリアによって結び付けられる。元々のクオリアは、ある刺激(縁)と本来それとは直結しない情動との関連を学習し、両者を連結する仕組みなのである。
一方、ヒトデには条件反射はないそうだ。(「ヒトデは学習しない。」愛媛大の宮脇恭史先生) ヒトデの場合、DNAによって決定された生得的な反応の仕組みに従い、例えば餌が拡散する化学物質によって正の走性が引き起こされるのであって、刺激(縁)と情動は直結しており、クオリアは必要ない。より正確に言えば、ヒトデはクオリアの仕組みを持たないので、生得的反応をするのみで、経験から学習することができない。
クオリアの仕組みが完成すると、それはすぐさま、利害に関わる対象を素早く見つけることにも活用されたはずだ。例えば、魚にとって餌となる虫の映像は、 化学物質である匂いのように直接生得的に摂餌行動のスイッチを入れるものでは、本来ない。餌を眼で見て捕食することは、餌の映像を条件(縁)にして捕食の 情動を起こすことであり、厳密にはやはり条件反射である。
<ものを見てそれが何であるか分かる>ということが条件反射であることを示す事例。20年ほど昔だったか、こんなドキュメンタリー番組を見た(確かNHK-TV)。小学生くらいの子供のいる、目の不自由な男性が、手術を受けて目が見えるようになる。しかし、象の置物を目の前に置かれていくらながめても、それが何か分からない。ところが、手でなでると、すぐに「あぁ、象ですね」と分かる。象の形は知っているのだ。男性は、子供といっしょにあちこち出かけ、教えてもらって幼児のように「これは何、あれは何」とひとつずつ目に焼き付けていく。つまり、視覚があるだけでは十分ではないのである。それだけでは、意味のない色と形のモザイクに過ぎない。そこにすばやく、いうなれば意味のある輪郭線を引く(ふさわしいクオリアを被せる)ためには、練習を重ねてスキルを身につけなければならない。すなわち、ひとつひとつ対象カテゴリーごとに条件反射を形成していくのだ。言い換えれば、さまざまな意味ある対象を感知する視覚クオリアをつくっていかねばならないのである。
(ということは、進化の系統樹の上で、発達した眼をもつためには、それ以前に条件反射ができるようになっていることが前提となる筈だ。眼のないヒトデに条件反射はなく、眼のあるコイにはあるという事実は、この仮説の傍証となろう。では、その中間のナメクジウオはどうなのだろうか? 二人の先生にお尋ねしたが、どうやらまだそこまでナメクジウオの研究は進んでいないようだ。発達した眼を持つタコ、イカ、あるいはエビ、昆虫は、条件反射をするのだろうか?)
【2007,4,12,加筆】 ネットで少し調べてみたら、ナメクジ、アメフラシ(ともに軟体動物)、ゴキブリなどで条件反射は確認されているようだ。
一旦クオリアができあがると、さらに、捕らえた獲物の感触・味などの直接的刺激も、情動と結びつけて留められる。こうして、クオリアは、本来の「条件反射を可能にする刺激と情動の連結」から、「情動と結びついた質感」へと拡張する。この派生的クオリアは、いちいちの経験を一から感受して反応するのではなく、刺激をカテゴリー化して素早く反応するという効果をもたらす。また、例えば腐った食べ物の味など、異常を素早く感知することにも役立つだろう。さらに、人間においては、言語や社会や文化の発展によって、感知される対象は極めて繊細・ 微妙となり、対応するクオリアも同様に繊細かつ複雑・多層化する。通常クオリアとして問題とされるのは、人間におけるこのような発展したクオリアであり、 もともとの形ではない。いきなり発展し複雑化したものから考えようとするから、収拾がつかなくなるのだと思う。
ともあれ、本来のクオリアであれ、発展したクオリアであれ、共通する本質は、刺激(縁)と情動との連結という点である。
ここでひとつ強調しておかなければならない重要なことは、クオリアは本来的にカテゴリーを検出する仕組みだ、ということである。元々のクオリアの機能は、利害に関わる(情動を引き起こす)事態を予告する縁を検出し、いち早くふさわしい情動を立ち上げることであった。池のコイの場合で言え ば、餌を予告する「手を打つ音」を検出し、摂餌の情動を起動する。しかし、手を打つ音は、人によって、時によって、様々に異なる。その違いを敏感に聞き分けていたのでは、条件反射は成り立たない。かといって、的外れの音に興奮するのは、無駄であるし危険でさえあるだろう。つまり、クオリアのもうひとつの役割は、反応すべき縁と反応すべきでない縁とを的確に分けることだ。いわば、その境目に境界線を引くことであり、境界線の内側における現象間の差異にこだわることは、かえって有害となる。従って、クオリアは、対象カテゴリーを代表するイデア的な一般性・抽象性を本質としている。クオリアの「とらえどころのなさ」はここに起因する。
経験を繰り返すことで、クオリアによって検知されるカテゴリーはどんどん精緻化されていく。つまり、境界線は精密になっていく。その結果、例えば、スレたブラックバスは、本物の餌とルアーを鋭く見分けるようになる。しかし、どんなに精緻化され、あるいは細分化されたとしても、クオリアによって検知されるのは、現象自体ではなく、あくまでカテゴリー、境界線の内か外か、であり、内側における差異は捨象される。
『ジャン・ピアジェ』p154から抜粋。「対象は存在していますが、その特性を発見するには漸近による他ないのです。…絶え間なく対象に 近づきますが、…決して到達はできないのです。」 これは、「カテゴリーを細密化していくことで対象に近づいていくことはできるが、現象自体には到達できない」と言っているのだと思う。
自閉症サヴァンの少女ナディアが5歳で描いた驚嘆すべき馬の絵は、ダ・ヴィンチも顔負けだ。それに対して、8歳の「健康な」少女の描く馬は、悲惨なほどに平板である(ラマチャンドラン『脳の中の幽霊』角川書店 p249)。この平板さは、クオリアがイデア的・抽象的であって具体性にかけることの現われだと思う。「健康な」少女は、自分の中の馬のクオリアをそのまま絵にしたのだ。健康であるためには、平板化し「いつも化」するクオリアが必要なのである。
しかし、その一方で、クオリアは、「具体的・直接的で生々しい」とも言われている。これは、今言ったことと一見矛盾するように聞こえる。その理由は、クオリアが動物個体の情動と結びついているからではないだろうか。クオリアの「生々しさ」は、対象ではなく、情動に由来する。生々しいのは対象の質感ではなく、実は我々の情動なのである。
『受動意識仮説』P59で、前野氏は、オーグメンティッド・リアリティという考え方を提示している。それは、「バーチャル・リアリティ研究の一分野」で 「画像や注釈のような情報を環境の上に重ねあわせることによって、仮想世界のリアリティを増大させる方法」だという。そして「視覚受容器が検出しているのは、何の意味も持たない画像」であるが、そこに「あわせて表示された、生き生きした「赤いリンゴ」のクオリアを同時に感じている」と解説している。
この考えにわたしも賛同する。ただし、クオリアがしていることは、リアリティの増大ではなく、逆のこと、すなわち、本来は個別的一回的である現象をイデア化、抽象化、平板化することである。そして、もうひとつの機能は、ふさわしい情動の立ち上げだ。
感覚受容器が捉えた刺激(縁)は、その時点では一回限りの個別的な現象であり、格別の意味はもたない。しかし、免疫システムにおける抗原のように働いて、対応するクオリアを刺激したとき、利害に関わる(情動を引き起こす)対象として検知され、価値的にニュートラルな刺激の上に、カテゴリーを象徴するイデア的クオリアが被せられる。同時に、対応する生々しい情動が起動され、ふさわしい反応が全身を走る。
例えば、野原の踏み分け道を歩いていて、突然ぎょっとして飛び退り、ヌラッとした鱗のテクスチャが稲妻に照らされたごとく脳裏に浮かぶ。恐る恐る確認し てみると、古びたロープの切れ端だったと分かって、ほっと胸をなでおろす。この場合は、ロープの画像にヘビのクオリアが被せられ、それが反応を引き起こし たのである。
我々は、なにかを感受するとき、ありのまま(如)の、格別の意味を持たない素の刺激ではなく、それまでの経験によって形成され情動と結合したイデア的ク オリアを感受している。先に述べたように、眼にしても、素の映像を感受するためのものではなく、条件反射を活用して利害に関わるカテゴリーにあてはまる現 象を、そのカテゴリーにあてはまるかだけに注目して、素早く見つける仕組みであった。
一部の人は、「クオリアというものは、我々が何かを感受するとき、その対象の側にあって、対象から我々にむかって発せられているものだ」と思っているか もしれない。あるいは、クオリアを、なにか「純粋経験」とでもいうべき、対象との生の接触のように考える人もいるだろう。しかし、クオリアは、対象に属するものではなく、我々の側にあり、かつての経験によってあらかじめ用意されているのだ。すなわち、我々は、現象を現象のまま、あるがまま(如)に受け止めたことなど一度もなく、常に自分にとっての利害とともにカテゴリーとして感受しているのである。
執着や差別というような型に嵌ったものの見方は、クオリアによる。イスラム教徒と聞けば、単純かつ即座に「テロリスト」のクオリアを被せ る人もいるし、ユダヤ人と聞けば油断のならない謀略家だと思う人もいる。ジャップは卑劣で暴力的、女性を性的奴隷としてしか扱わない、と思っている人もずいぶんいるに違いない。さらにまた、こういった無反省な自動的反応を植えつけて、人々をうまく操ろうとする人もいる。政治的プロパガンダも広告も、こうし た狙いだ。しかし、操っているつもりの人も、賢しいつもりで自分では気づいていないが、執着(⊂クオリアに導かれた自動的反応)に操られているのである。
外の対象ではなく、内のクオリアに反応しているという認識は、唯識の考えと通底する。我々が感知しているのは、外の対象そのものではなく、外の対象によって励起されたクオリアである。ただし、「唯心であって外境などない」というソリプシズムではない。ソリプシズムは、唯我独「存」の考えであり、無我=縁起という釈尊の教えの対極だ。対象には漸近することができるだけで決して到達できない(ピアジェ)のかもしれないが、それでも対象が現象していることは前提されている。
我々が反応しているのは、感覚器官で捉えられたその時の生の一回的現象自体ではなく、その上にかぶせたクオリアである。そのことが、「いつも化」を引き起こす。クオリアは、それが検出するカテゴリーを象徴するイデア的イメージであった。クオリアによって、現象は本来の一回性・個別性を失い、いつもどおりに価値付けられたいつものものとして、実体視される。いつもどおりの価値を持つものとして、いつもどおりに対処される。
「いつも化」という言葉は、こなれていないので、もう一度説明しておくと、「実際にはそのつどの無常にして無我なる縁起の現象である対象を、変らぬ価値を備え、持続的に存在し続ける実体として捉えること」である。
ニコラス・ハンフリーは『赤を見る』p124から数ページをかけて、意識における時間の持続を問題にしている。しかし、これは、私たちが現象を感じる時、現象自体ではなく、そこに被せたクオリアを感じているのだとすれば、自明ではないだろうか。クオリアはイデア的性格を持ち、イデアに変化はなく、無時間的である。我々は時間の中で無数の縁に晒されており、その中のいくつかが対応するクオリアを次々と励起させていく。次の縁がクオリアを起動するまでの短 い時間、その時点のイデア的クオリアを感じている。このことが、ニコラス・ハンフリーの問うている持続性を生み出しているのではないだろうか。
いつも化は、凡夫の「健康な」対処の仕方である。であるならば、自閉症サヴァンのナディアにおいては、何が違うのだろうか? 本当はしっかりとした記録に基づいて分析しなくてはいけないのだろうが、ここまで述べてきたわたしの推論から想像すると、ナディアの場合は、クオリアの機能が十分でなく、「いつも化」が不徹底なのではないだろうか? 馬を描いているから対象化の機能はある。しかし、クオリアによるところの境界内の現象の「塗りつぶし」が完全ではなく、カテゴリーの内側にある差異が透けて見えてしまう。その結果、ダ・ヴィンチがデッサンを重ねてようやく「漸近」したところが、ナディアには初めから見えている。ナディアは、我々より「如」に近いところで生きていたのだ。
(それに対して、薬物や瞑想修行による変性意識体験では、ふさわしくないミスマッチのクオリアが被せられているのではないかと想像する。その結果、過剰な意味や異常な意味が湧き上がってくる。)
クオリアに絡めて、長々と書いてきた。
ここまでの推論によって、「気づくこと」とはどういうことか、手掛かりが得られたと思う。
「気づくこと」とは、クオリアがそれに当てはまる一回的な現象によってそのつど起動されることである。従って、池のコイは、手を打つ音に「気づいて」いる。(それに対して、経験に依存しない生得的な反射反応では、クオリアは関与しておらず、「気づき」なしに反応は起こる。)
◆2 ⅱ 意識 「気づいていることに気づくこと」
しかし、「池のコイに意識がある」と言い切ることには、私にもためらいがある。そう言い切れないとしたら、何が不足しているのか? 意識は、「気づくこと」では不十分なのか?
先にあげた、ロープの切れ端をヘビと見間違えた時の反応を考えてみよう。ロープの切れ端によってヘビのクオリアが起動され、ふさわしい反応(飛び退るこ と)が起こる。この反応は自動的であり、「ヘビだ」と思う(意識する)より早く発動し、終了している。意識は、クオリアの作動よりかなり遅い。意識=クオ リアの起動、ではない。
クオリアが起動されて反応が起こっているけれど意識のない状態の例をもうひとつ挙げるなら、欠神自動症がそれにあたる。ダマシオ『無意識の脳 自己意識 の脳』(講談社)p23に、「もぬけの殻」状態のまま、テーブルのカップをながめ、手に取って、コーヒーを飲み、立ち上がり、ドアに向かって歩き出した患 者さんのことが載っている。コーヒーカップが目に入り、コーヒーの香りに導かれて自動的に手が伸びて一口飲んでいるが、意識はない。ということは、「クオ リアが起動されて反応が起こること」(気づくこと)だけでは、やはり意識というには不十分だということだ。
つらつらと考えてみると、意識とは、「気づいていることに気づくこと」ではないだろうか?
ここまでの試行錯誤を当てはめて考えてみよう。「気づくこと」は、クオリアが起動されることであった。であれば、「気づいていることに気づくこと」と は、「いずれかのクオリアが起動されていること」を縁として起動される別のクオリアがあり、そのクオリアが起動されることである筈だ。この仮説を検討して みたい。
ニコラス・ハンフリーは、こんなことを言っている。『赤を見る』p97~から要約。
「原始的なアメーバのような生き物は、さまざまな刺激を受けると、その部分でそれに応じた局所的な「身悶え」の反応をする。
これが進化して中枢神経を持つようになると、感覚器官からの情報を一から分析するよりも、自分の反応をモニターするようになる。なぜなら、どこで刺激が起きているか、どんな種類の刺激か、どう対処すべきか、といった必須の情報の一切は、自分の反応の中に含まれているのだから。」
これを説明する比喩として、ニコラス・ハンフリーは、ジャン・コクトーの書いた一人芝居を挙げている。女性が昔の恋人と電話で話しているのだが、女性の受け答え(反応)だけで、電話の向こうの男がどんなことを言っているのか(刺激)は、手に取るように分かる。
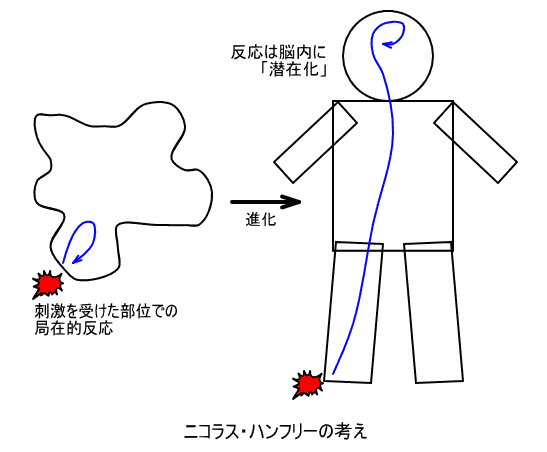
そして、『赤を見る』p105~、p134~で「刺激に対する反応回路が短絡していき、ついには脳内に潜在化してループを形成する」と言い、このような図を示している。p106
いろいろな発想を刺激してくれるユニークな仮説だ。しかし、私としては、「モニターする」という言い方が少々が気になる。デカルト劇場に座っているホムンクルスを想起させる我論的響きがあるからだ。とはいえ、刺激と自分の反応(すなわち情動)とを一体化してとらえる考え方はおもしろい。私のクオリアの定義に通底するように思える。
縁によって起こされる(=縁起)そのつどの(=無常)自動的反応(=無我)であることにこだわって、私の考えを図にすればこのようになる。野道にロープを見た場合を考えてみた。
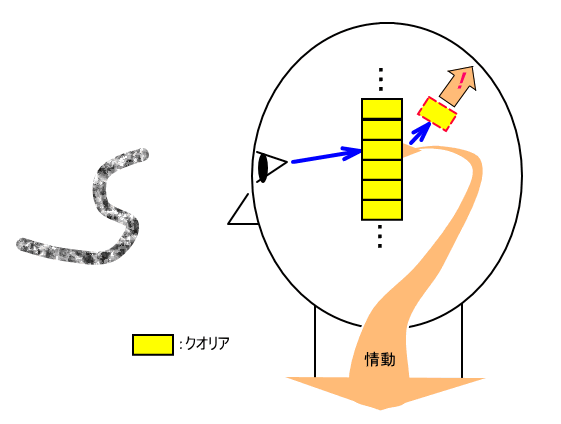
草や土と一緒に古びたロープの映像が視界に入る。この時点では、単に色と形が混ざったモザイク模様にすぎない。しかし、それが、過去に形成されたさまざまなクオリアのうち、ヘビのカテゴリーのクオリアを刺激すると、そこにヘビのイデア的イメージが被せられる。同時に、ヘビに出会った時にふさわしい情動が全身を走る。(もし、適当な大きさの丸いものが光れば、コインを見つけたときの情動がおきる。)ここまでは、欠神自動症や池のコイと同様、意識以前の自動的反応だ。そして次に、ヘビのクオリアが刺激されて情動が起きたそのことが、縁(刺激)となり、もうひとつのクオリア(赤い破線の枠)を起動し、「ヘビだ!」という「意識」が起こる。
よく「意識の指向性」ということが言われる。しかし、私は、意識が直接対象を指向するとは思わない。(「志」には、主体的なニュアンスがあり、違和感を感ずる。無我=縁起に反するのだ。よって、「志向性」ではなく、「指向性」という言葉を、私は使いたい。)
この図のとおり、対象と意識とは直接につながるものではない。両者の間は、「気づき」が媒介している。さらに厳密に言えば、「気づき」が起こるのも、直接対象によってではなく、対象に被せられたクオリアによってである。意識と対象との関係は、幾重にも間接的なのだ。<対象→クオリア→気づき→第二のクオリア→意識>である。
あらかじめ意識があって、それが何かを志向するのでは決してない。あらかじめ存在する意識が「ヘビだ!」と思うのではまったくない。「ヘビの情動が起こったこと」によって起こされる情動が意識なのである。前野氏の言うとおり、意識は受動的である。意識(第2の情動)は、第1の情動によって、第1の情動の後に起こされる。リベットの実験で、「意図(⊂意識)」よりも先に反応の信号が発信されている、というのは、このことの現われだ。
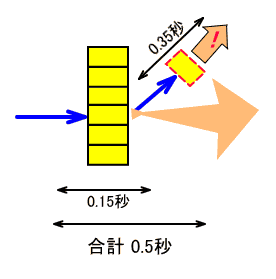
リベットの実験で、「意図する 0.35秒前に既に行為の信号はスタートしている」というのは、「第一のクオリアが情動を起こしてから、そのことが第二のクオリアを起動して意識が生じるまで 0.35秒かかる」ということを示していると思う。そして、リベットのもうひとつの実験、「感覚を感じるのに 0.5秒かかる」というのは、「第一のクオリアが情動を起こすのに 0.15秒かかる」ということではないだろうか。つまり、第一のクオリアで0.15秒、第二のクオリアで0.35秒、合計 0.5秒ということだ。
(2008,1,12,加筆:実はこれを書いた時点では、リベットを読まずに聞きかじりだけで書いていた。その後『マインド・タイム』を読んで、その感想を小論《ベンジャミン・リベット『マインド・タイム』を読んで》に掲載した。)
意識は、<縁がクオリアを刺激し情動が発動したこと>が第二のクオリアを起動して立ち上がる第二の情動であり、決してあらかじめ存在するのではなく、そのつど新たに起こるのである(無常=無我=縁起)。さらに別の言い方をすれば、意識とは、条件反射したことを縁(刺激)とする、脳の中に「潜在化した」条件反射であるということもできる。
気づいていてしかも意識はあるのに、気づいていることに気づくことができないという特殊な事例は、盲視だ。視野の中の盲視となったエリアにおいて何かが飛んでくると自動的によける(情動が起こる)のに、「本人」(意識)には何も「見えていない」。(おそらくは脳の視覚野において)第一のクオリアは問題なく機能し、ふさわしい情動が起こっているが、そのことが第二のクオリアへと連結されない。ニコラス・ハンフリーは、人間における盲視が発見される前に、サルにおける盲視を発見した人で、『赤を見る』には、盲視に関する興味深い事例がいくつか紹介されている。
「見えない」のに、よけることができるのは、こびとたち(ノエシス)の自動的な働きの証左でもある。意識を持たない動物たちは、これと同様、意識なしに状況に自動的に対応している。条件反射のない動物においては、気づきさえなく、生得的な自動的反応だけで対応している。そして、こういった反応の仕組みは、人間のような発達した動物においても、しっかりと機能しているのだ。より正確には、私たちという反応のほとんどは、このような意識以前の 自動的反応によって営まれている。「わたし」という偉そうな意識は、喩えるなら、湧き上がってくる噴水(ノエシス)の上で震えているちっぽけなピンポン球のようなものだ。もっと正確に言えば、ピンポン球も存在せず(あればホムンクルスになってしまう)、噴水の先端に次々と躍り上がる水滴の断続的なきらめきのようなものなのだ。(小論、《自分という現象について》冒頭近くを参照ください。)
◆3 「わたし」という意識
では、いよいよ「わたし」という意識の発生について考えなければいけない。「気づいていることに気づくこと」が、そのまま「わたし」という意識だ、と 言ってしまいたい誘惑にも駆られるが、それはちょっと乱暴であろう。 「気づいていることに気づくこと」が意識であるが、それは、まだ「わたし」という意識 ではない。
(自嘲の意味も交えて)「飛躍」の前の準備運動ということで、興味を惹かれるが断片的な知識のまま取り込めていない事柄をメモしておきたい。
レスリー・J・ロジャース『意識する動物たち』(青土社)によれば、人間以外の動物で自分を対象化できるかもしれないのは、サル、鳥、イルカなど、としている。(鏡に映った自分の姿を見て、鏡ではなく自分の身体に関心を向けるか、という実験による。)人間の個体発生においては、月齢18~24ヶ月以降だという。(同書p30~)
ピアジェの見解。赤ちゃんは、初め、自己中心性(「認識する行為中において主体が自分自身を知らず、更には客体の方に向いて自分を中心からはずすということに到達しない時の主体と客体との混一」<仏教的に言えば、「主客未分」か>)の状態にあり、「ものはそれ自体として存在せず、赤ん坊は主体としての自分を意識していない」が、1歳半くらい(レスリー・ロジャースの見解と同じだ)でコペルニクス的転回が起こって、「主体の活動は、徐々に分化し、多様化し、統合化していき」「主体の観念が作られ」「永続的対象の観念が作られる」という。(『ジャン・ピアジェ』p50~)
やはりどうやら、主客は同時に対生成するようだ。そして、そもそもの最初から、対象は、無常なる「現象」のままにではなく、いつも化され、永続的なもの、つまり「存在」として設定される。
系統発生においては、対象検知は、クオリアによるカテゴリー検出(条件反射)であり、現象を現象のままに見ることは、かえって不利であった。おそらく個体発生においても事情は同じであろう。現象を現象のまま、変化するそのつどの現象として見ることは、自然のままでは起こりえない。クオリアによって、現象にカテゴリーを象徴するイデア的無時間的イメージを被せ、いつも化することが、対象認知には必要なのだ。経験を重ねてクオリアを精緻化していけば、クオリアを現象に近づけていくことはできるが、現象自体にはけして到達できないのかもしれない。ピアジェは、漸近といい「絶え間なく対象に近づくが、決して到達はできない」といっている。
話がずいぶん錯綜してきた。これまで検討したことを簡単に振り返ってみよう。
そのままでは格別の意味を持たない現象が、縁となって、クオリアを起動し、条件反射の仕組みによって情動を起こす。これが「気づき」であった。さらに、このことが縁となって、第二のクオリアを励起させておこる反応、それが意識であった。
「うわぁ、ヘビだ!」という意識は、クオリアを介して間接的であれ、ヘビを対象にしている。ヘビを内容としている、と言ってもいい。しかし、「うわぁ、 ヘビだ!」は、単なるヘビの表象ではない。意識は、情動も含んでいる。言うならば、「うわぁ、ヘビだ!」の「うわぁ!」の部分である。草むらにコインを見つけたら、「おっ、しめた」が情動だし、ウンチなら、「げっ、汚ね」が情動だ。意識は、常になにがしかの情動(身体の状態の変化)を背景として含んでいる。このことが、意識を私的で主観的なものにしている。また、「わたし」という意識の生成にも、このことは関連があるのかもしれない。多分そうだろう。ともかく、まだ明確に掴めていないが、意識の背景を情動が染めていることには、なにか重大な意味・影響があるような気がする。しかし、とりあえずの叩き台の仮説としては、もっと単純に考えることにしよう。
「わたし」という意識が発生したのは、ヘビその他のクオリアのリストに、「わたし」というクオリアが追加されたのだ。
この小論の冒頭近くで、「わたしという反応は、たくさんのノエシスが連鎖し、重なり合い、もつれ合って生じている」と書いた。そのほとんどのノエシスは、気づかれることもなく、黙々と密やかに遂行されていく。しかし、中には大きな情動を引き起こすノエシスもある。例えば、何かをうまくしとげたときの「よし、やった!」とか、失敗したときの「いかん、ダメだ!」といった情動を起こすノエシスだ。ノエシスによって大きく情動が動いたことが、池のコイにおける手を叩く音の場合と同様に条件反射を形成し、「わたし」というクオリアが生み出される。それ以後、情動を起動するノエシスにはイデア的無時間的な「わたし」というクオリアが被せられるようになる。その結果、そのつどの現象であるノエシスは、「わたし」へといつも化される。
そして、ノエシスが「わたし」のクオリアを起動して情動が起こったことが縁となって、第二のクオリアを起動し、「わたし」という意識が起こる。
強調しておきたいのは、「わたし」という意識は、持続的に存在するのでは決してなく、時々に縁があったときにだけ現象する(無常=無我=縁起)、ということである。また、「わたし」という意識の内容は、現象自体であるノエシスではなく、「わたし」というイデア的無時間的なクオリアである。ロープの切れ端のモザイク映像が目に映って、「わっ、ヘビだ!」と思う場合とまったく同様だ。先ほどの図を思い出して欲しい。
このあたり事情の説明するには、こういう比喩がいいかもしれない。パーティ用の小物で半透明のマスクが売られているのをご存知だろうか。 それをかぶると、ひとりひとり違う顔で生き生きとした表情が、変化のない同じ顔になってしまう。私達は、せっせせっせとさまざまに忙しく働いているのだか、自分を見るときには、さっと素早くそういったマスクを被せてしまうのだ。その結果、そのつどそのつどさまざまに働くノエシスが、「いつものわたし」に いつも化されるのである。
◆4 ノエマ自己 反省・努力
前段で、「わたし」というクオリアを刺激するようなノエシスが働いたとき、「わたし」という意識が生じる、と書いた。「わたし」というクオリアを刺激す るノエシスは、外面的な行為ばかりではない。記憶の想起や連想も、「わたし」というクオリアを刺激し得る。進化の過程でヒトが生まれてくる道筋において、 エピソード記憶や連想といった能力も平行して進化してきており、それが縁となる。
念のために…。記憶の想起や連想もまた、湧き上がってくる泉の水のごとき縁による自動的反応である(最初の図。ノエシスの赤い矢印)。このことは、座禅をすれば妄想として嫌というほど実感できる。
差し迫った事態が生じていないとき(=眼前の現象がどのクオリアも起動しないとき)、エピソード記憶がクオリアを励起することがある。さらにまたその中には、「わたし」のクオリアを刺激し、「わたし」という意識を起こすものもある。かつての「わたし」の振る舞い(ノエシス)が、「わたし」のクオリアを被せられ、その時の情動とひとつになって想起される。悔恨の情動をともなうことも多いだろう。
また、悔恨などの情動が強ければ、それをもたらしたかつての自分の振る舞いが、眼前で進行する他のさまざまな縁に勝って、クオリアを獲得し、「わたし」という意識が生じる場合もあるだろう。
「わたし」という意識は、「わたし」というクオリアを対象としている。そして、クオリアは、イデア的無時間的であった。そのため、固定的無時間的な「わたし」が対象化され、実体視されるに至る。それがノエマ自己だ。
人は、しばしば「本当の自分」とか「あるべき私」とか「本来の自己」といったことを言う。本当の「本当の私」は、そのつどそのつど具体的に働いている無数のノエシスである筈だ。しかし、我々が口にするところの「本当の私」は、本当は「本当の私」ではなく、「わたし」という、平板で抽象的イデア的なクオリアを対象にして実体視して作り上げられたノエマ自己なのである。
そして、ノエマ自己は、いうなれば、将棋の駒のような役割を果たす。終局の後の検討のように、エピソード記憶が次々と浮上し、ああすればよかったか、こ うすればどうだったか、とシミュレーションが行われる。あるいは、別の比喩を挙げれば、ノエマ自己は、粘土で作る自分の塑像のようなものだ。「もう少し足を長く」、「いや、もっと短い」、「こっちはどうだ・・・」。こうして自己像が評価・検討される。
そして、ノエマ自己に問題点・改善点が見つかれば、自動的必然的に反省・努力の情動が起こる。
ピアジェによれば、反省ということが現れるのは、7歳半前後だという(『ジャン・ピアジェ』p24)。私自身を振り返れば、ノエマ自己による自己改造がもっとも激しく遂行されるのは思春期だと思う。思春期における自己改造は、昆虫の変態にも喩えるべきあまりにも過激な改変で、時には失敗して破壊的な結果となる場合も多い。
そもそも生命とは、反応の組み合わせを維持拡大するような反応の組み合わせであった。それゆえ、あらゆる生物は、その時その時の状況に応じて、常に「持続しよう、拡大しよう」と反応する。「もがき足掻き反応」と私が呼ぶものだ。進化の初期(といっても時間的には非常に長いが)においては、DNAに決定された、種に共通な生得的な能力によってのみ、状況に反応していた。第二段階として、頭索類(ナメクジウオなど)か無顎類(ヤツメウナギなど)のあたりで、条件反射が可能になり、動物個体単位で、経験によって反応パターンが向上するようになった。さらに第三段階、ヒトまで進化が進むと、ノエマ自己によるシミュレーション・反省・努力の仕組みが生まれ、状況への適応はさらに大幅に向上した。
(この後さらに第四段階として、言語・文化・教育などによって、適応の術はグループに共有・蓄積され、適応は格段に進む。しかし、このことは、この小論のテーマから外れる。)
念のためしつこく指摘しておきたい。シミュレーションも反省も努力も、いかに複雑に進化したものであれ、やはりノエシスの組み合わせであり、そのつど縁によって起こされる自動的もがき足掻き反応である。(無常=無我=縁起)
◆5 執着・発心・精進 釈尊の教え
ノエマ自己によるシミュレーション・反省・努力は、生命であること、すなわち持続・拡大しようとすることに根ざしている。持続し拡大しようとする生命本来の強い傾向が収斂したシンボルがノエマ自己である、とも言えよう。ノエマ自己は、「わたし」というクオリアを内容としており、当然それにふさわしい情動が染み込んでいる。「わたし」というクオリアが条件反射で引き起こす「わたしにふさわしい」自動的反応が我執である。
また、我々が対象として捉えているものも、すべて実は縁(現象)によって起動された無時間的イデア的クオリアであり、情動をどっぷりと含んでいる。より正確には、情動を引き起こすものがクオリアを刺激するのだ。そのため、対象は、好悪の価値を備えたまま変らずに存在するものとしていつも化される。あらゆる対象は、程度の差こそあれ、獲得すべきもの、あるいは排除すべきものとして情動を引き起こす。この情動が執着だ。
シミュレーション・反省・努力は、執着を実現するために行われる。工夫をすることも、人を欺して儲けようとすることも、資格を取ろうと勉強することも、世間で肯定的に評価されることであれ、否定的に評価されることであれ、どれも執着に駆動された反応だ。執着に駆動されたシミュレーション・反省・努力は、確かに短期的には競争に打ち勝ち、生命として持続・拡大することに大変有利に働く。しかし、時としては、かえって大きな苦をももたらす。我々は、時間の中で死につつある現象であり、無限の持続・拡大を目指しても、必ず破綻する。一時的な快を実現しても、それは、逆に苦を深める結果になる。(旧サイトの小論《一切皆苦は快を含む。凡夫は執着依存症》 参照。)このことは、普段なかなか気づくことはできないが、その事実に直面せざるを得ない場面はしばしば起こり、その時、人は、ノエマ自己によるシミュレーションでなんとかその事態に対応しようとする。世の東西を問わず、生の無意味さや苦は問われ続け、対応がシミュレートされた結果、道徳や宗教が生まれた。
道徳や宗教は、我執に置き換えて、家や国家や神などへの執着を据えるものであり、我執がもたらす苦をいくらか減らすことには成功したかもしれない。しかし、家や国家や神は、執着の集団化・組織化をもたらし、時として我執とは比べ物にならない巨大な苦を生み出している。あるいは、家や国家や神への執着が、 誰かの我執に利用されるのだ。
世界史に多く現れた道徳家・宗教家の中で、唯一釈尊のみが、苦の原因は執着であることを見抜かれ、執着の対象を置き換えることではなく、執着そのものを根絶( or 弱体化?)することで、苦の生産を止める( or 抑制する?)ことを説かれた。執着の発生するメカニズムを観察・分析して、無常=無我=縁起を発見された。我々は、そのつど縁によって起こされる無我なる現象であるのに(この小論で述べ たことだ)、変わらぬ価値をもって存在し続けると誤って思い込んでいること(無明)が執着の原因なのである。無明を破るためには、自分がそのつど縁によっ て起こされる無我なる現象であることを観察し、腑に落ちて納得しなければならないのであるが、そのための段階を踏んだ具体的カリキュラムも、三学(戒・ 定・慧)や八正道という教えで残してくださった。
修行中の釈尊は、苦の原因をさまざまに分析された。すなわち、ノエマ自己によるシミュレーションを徹底的に繰り返し、努力を重ねられた。ノエマ自己を手段として活用することによって、逆にそのノエマ自己を実体視すること(我執)が苦の原因だ、と発見された。
客観的知識としてではなく、自分のこととして無常=無我=縁起を腑に落ちて納得することは、簡単なことではない。そのためには、ノエマ自己を活用した反省(発心)と努力(精進)が必要である。その果てに、「「わたし」は妄想にすぎず、実体としては存在しなかったのだ」と気づき、無常=無我=縁起を自分のこととして腑に落ちて納得できたとき、執着は停止し、寂静なる涅槃の状態になる。
釈尊の最期のお言葉は、「怠ることなく修行を完成なさい」だった(中村元『ブッダ最後の旅』岩波文庫)。怠らずに精進することがなければ、縁のままに執 着の反応の繰り返しであり続け、利得を目指してかえって苦を作り続けることになる。苦の生産を止めたければ、正しい努力(精進)が必要である。
我々は無我であり縁起であるのだから、我々が第一原因となってなにかを開始することはありえない。主体性は錯覚だ。努力もまたノエシスである以上、縁によって受動的自動的に生まれる反応である。しかし、その言明だけを聞くと、逆の縁となって作用しかねない。聞いた人は、「じゃあ、それまでは努力などせずに待っていよう」という反応になってしまう。だから、「執着に導かれた努力ではなく、無常=無我=縁起を知るための正しい努力(正精進)をせよ」と言わねばならない。この教えが良き縁となって、精進を引き出す。仏教とは、無常=無我=縁起という教えと、それを納得するための精進の勧めとを、良き縁(良きミーム)として広めることによって、世の苦を減らすことなのだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【2007,4,12,加筆】
上を掲載した後、池谷裕二『進化しすぎた脳』(講談社ブルーバックス)を読んだ。刺激的で大変おもしろかった。
一定のカテゴリーに属する縁と一定の情動とを結び付けるクオリアが形成され条件反射が実現されるのは、シナプス可塑性によると考えるが、シナプス可塑性を実現するNBDA受容体のメカニズムには感嘆させられたし、大脳皮質のニューロンは深い睡眠の時に最も活発に活動しているなど、脳の自発発火・ノイズ活動の話にも興味をそそられた。つつかれたヒルは時によって違うパターンで逃げるが、その違いはどのようにして発現するか、というのも、刺激的でいろいろ考えさせてくれる。
しかし、クオリアに関しては、池谷さんは私とはぜんぜん違うことを言っておられる。
- たぶん、クオリアもまた言葉によって生み出された幻影なんだと思う。(P173)
- クオリアは大脳皮質で生まれるんだろう。(P176)
- 感情の多くは、つまりクオリアの多くは言語の産物だろうから、(動物は)人間ほど豊かな感情は持っていないと僕は考えている。(P178)
- 意識とか心というのは多くの場合、言葉によって生まれている。意識や心は言語がつくり上げた幽霊、つまり抽象だ。・・・意識とか心は<汎化>の手助けをしているんだよ。・・・つまり、「言語→心→汎化」だ。(P196)
池谷さんは、クオリアを感情なども含んだかなり高次なものとして捉えておられ、言語以降に出現すると考えておられる。一方、私は、遅くとも魚かそれ以前の段階で出現している、もっとプリミティブなものだと考えている。この違いは、考えの違いというよりも、クオリアをどういうものとして捉えるかの違いであり、同じクオリアという言葉で違うものを考えているのだと思う。だから、本質的に対立しているとは思わない。
ただ、<汎化>に関しては、私の考えは池谷さんとははっきりと異なる。汎化は、言語以降ではなく、条件反射によって利害に関わる現象をカテゴリーとして対象化し始めたそもそもの最初から(つまり魚かそれ以前から)、既に始まっている、と考える。我々が汎化せずに、すなわち個別的現象を個別的現象のまま価値付けなくありのままに捉えたことは、進化史上一度もない。
このことに私がこだわる理由は、「計らいを捨てさえすれば、かつてあった執着のない完全な状態に戻ることができる」と誤解している「仏教」が多いからである。涅槃は、凡夫にとって未だかつて実現されたことはなく、努力して(=計らって)未来に実現すべきものなのだ。「完全な状態がかつてあった」と考えるのは、梵我一如思想であり、反仏教である。梵我一如に関しては、2004,6,24,の和バアさんとの意見交換などを参照。
一方で、池谷さんに補強していただき勇気づけられた部分も大きい。
- 大脳皮質の第一次視覚野が網膜から受け取っている情報は、…なんと全体の3%しか、外部の情報が入ってこないことになる。残りの97%は、脳の内部情報なんだよね。
- トップダウン処理が働いて「これは机なんだ」と信じ込ませるような強力な機構がないと、机を机とする安定した認識は生まれない気がする。…(学生)記憶と、記憶の中にあるカテゴリー化ですね。…机とはかくあるものという情報が記憶の中に保管されていて、網膜からあがってきたわずかな情報を手がかりにして、「机」だと思い込むための機構が作動する。
「生の視覚刺激は無意味な色と形のモザイクにすぎないが、それがクオリアを起動し、クオリアが被せられ、我々はそれを意味ある映像として見ている」という私の考えは、これらに適合するのではないかと思う。「記憶の中に保管された情報」というのは、私の場合、「経験することで形成された条件反射」ということになるが…。
また、池谷さんのホームページでみつけた次のような文章にもなるほどと思った。
・・・ヒトの感覚や運動に関与する神経細胞(神経システムの外部接点)は1千万個ほどであるのに対し、システム内部の神経細胞(広義でのインターニューロン)はそれを遙かに凌駕する1千億個が存在する。しかも、内部結合のパターンは単純な順次経路からはほど遠く、高度に再帰的であり、さらに、常に自発的に活動している。
つまり、外部環境は神経システムの内部ダイナミクスをわずかに変化させることはできるが、その状態を特定することはできない。「外部環境が神経システムに反応を惹起させる」などと捉えるのは、神経科学者の傲慢に起因した誤解にほかならない。
この意味で、多くの科学者が暗黙に了解している前提、つまり、「脳はいわゆる”I/O装置”である」とするは、明らかに誤りであるし、議論をすり替え真理から逃避するものである。神経システムは、環境の情報を抽出しているのでない。そうではなく、環境に潜むどんな情報が、神経システムの状況にどんな攪乱を引き起こすかを、システム個体の歴史を鑑みることで決定し、これによって特定の世界を生起させているというのが、正しい視点である。神経システムは、環境と相互にカップリングすることで、自発的に軌道(アトラクター)を生み出し、その上を遷移していくという、連続的かつ安定的な運動システムである。環境とシステムの相互作用の仕方は、過去、すなわち、環境とシステムがいかなる歴史を経験してきたかによって決まる。
ここで「歴史」とか「過去」とか言われているのは、経験によって蓄積された条件反射ではないだろうか?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ご批判・ご教授をお願いします。
曽我逸郎


